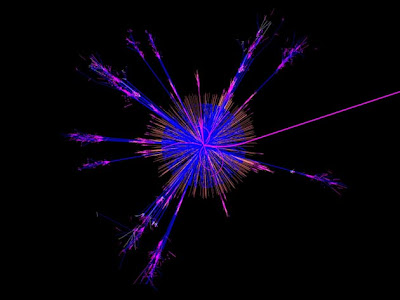不況が続くとインチキや引っ掛け、詐欺・窃盗の類いが増える。普段は善良な人々がちょっとした誤魔化しを行い、平均的な人物は悪事に手を染めやすい。悪い連中に至っては被災者を騙すくらいのことを平然とやってのける。
出版不況も長期化している。で、このようなデタラメ極まりない副題をつけるに至るってわけだよ。まあ酷いね。悪質だ。せっかくの内容を台無しにしてしまっている。
そもそも原題は「“blink”=ひらめき」(訳者あとがき)である。マルコム・グラッドウェルは「ひらめきが正しい」と主張しているわけではない。「正しい場合もあるし、誤るケースもある」と書いているのだ。このため副題を刷り込まれた読者は、内容にチグハグな印象をもってしまう。後半になると「あれ、どっちなんだ?」と混乱するのだ。光文社の罪は大きい。
これから本書を読もうとする人には、「副題をマジックで消すこと」をお勧めしておこう。
フェデリコ・ゼリもイブリン・ハリソンもトマス・ホービングもゲオルギオス・ドンタスも、みんなそれを見たとき「直感的な反発」をおぼえた。そのひらめきに狂いはなかった。わずか2秒、文字通り一目で、その像(※紀元前530年頃に作成されたとするクーロス像)の正体を見抜いたのである。ゲッティ美術館の鑑定チームは14か月かけて調べ上げたが、彼らの2秒にかなわなかった。
本書『第1感』は、この最初の2秒にまつわる物語である。
【『第1感 「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい』マルコム・グラッドウェル:沢田博、阿部尚美訳(光文社、2006年)以下同】
紛(まが)い物といえば骨董品である。有名な美術館であっても偽者をつかませられることがあるようだ。ま、書画骨董の類いは、どことなく信仰と似ている。自分が信じる限りは救われるのだ。
ところが一流の目利きといわれる人は一瞬で真贋(しんがん)を見分ける。見分けるのだが、具体的な言葉で説明することができない。言葉は思考であり意識であるから、きっと無意識領域で違和感を覚えるのだろう。確かに胡散臭い人物と出会った時などは、「どこがどうってわけじゃないんだが、あの野郎は嘘の臭いがプンプンしていやがるぜ」ってなことが多い。
果たして脳機能から見ると、どのようなメカニズムが働いているのか?
このように一気に結論に達する脳の働きを「適応性無意識」と呼ぶ。心理学で最も重要な新しい研究分野のひとつである。適応性無意識は、フロイトの精神分析で言う無意識とは別物だ。フロイトの無意識は暗くぼんやりしていて、意識すると心を乱すような欲望や記憶や空想をしまっておく場所だ。対して適応性無意識は強力なコンピュータのようなもので、人が生きていくうえで必要な大量のデータを瞬時に、なんとかして処理してくれる。
わかりにくい説明だ。これではヒューリスティクスと変わりがない。コンピュータのようなもの、とは並列処理ができるという意味だろう。取り敢えず「ひらめき=適応性無意識」と憶えておけばいいと思う。
次に具体的な実験例を示す。
初対面の人に会うとき、求職者を面接するとき、新しい考えに対処するとき、せっぱつまった状況でとっさに判断しなければならないとき、そういうときに、私たちは適応性無意識に頼る。たとえば学生の頃、担当教官が有能かどうかを判断するのに、私たちはどれくらいの時間を費やしただろう。最初の授業で? それとも2回目の授業のあと? 1学期の終わり?
心理学者のナリニ・アンバディによれば、学生たちに教師の授業風景を撮影した音声なしのビデオを10秒間見せただけで、彼らは教師の力量をあっさり見抜いたという。見せるビデオを5秒に縮めても、評価は同じだった。わずか2秒のビデオでも、学生たちの判断は驚くほど一貫していた。さらに、こうした瞬時の判断を1学期終了後の評価と比べてみたところ、本質的な相違はなかったという。(中略)これが適応性無意識の力である。
ここがポイントだ。経験や学習の後に下した判断と、第一印象の判断に相違はない。つまり相手を判断するための情報は量よりも質が問われることを意味する。
綿密で時間のかかる理性的な分析と同じくらいに、瞬間のひらめきには大きな意味がある。このことを認めてこそ、私たちは自分自身を、そして自分の行動をよりよく理解できる。
女の直感だ。そして女は直感の奴隷でもある(笑)。
横方向に合理の世界は広がり、縦方向に直観的英知(ひらめき)が走るのだろう。稲妻のように。
実験例をもう一つ紹介しよう。
この実験(サミュエル・ゴスリング)から、一面識もない人物のことを15分間部屋を観察しただけで、長年の知りあいよりも理解できるものだということがわかる。ならば「相手をよく知る」ために会合や昼食を重ねても無駄だ。私を雇っても大丈夫かどうか知りたければ、私の家を訪ねてきて、部屋を見ればいい。(中略)
この実験も「輪切り」の一例にすぎないのだ。
「輪切り」とはMRI(磁気共鳴画像)に掛けた言葉だ。英知の閃光が見えない内部をも照らすってわけだ。要は「一をもって万(ばん)を知る」ということなんだが、どこに注目するのかが問題だ。しかも相関関係はあったとしても、そのまま因果関係と断定するわけにはいかない。
・相関関係=因果関係ではない/『精神疾患は脳の病気か? 向精神薬の化学と虚構』エリオット・S・ヴァレンスタイン
医者の訴訟リスクは何に由来するのか? この辺りから副題が邪魔になってくる。
実を言うと、医者が医療事故で訴えられるかどうかは、ミスを犯す回数とはほとんど関係ない。訴訟を分析したところ、腕のいい医者が何度も訴えられたり、たびたびミスしても訴えられない医者がいることがわかった。一方で、医者にミスがあっても訴えない人がかなりの数に上ることもわかった。要するに、患者はいい加減な治療で被害を受けただけでは医者を訴えない。訴訟を起こすのにはほかに「わけ」がある。
その「わけ」とは何か。それは、医者から個人的にどんな扱いを受けたかである。医療事故の訴訟にたびたび見られるのは、医者にせかされたとか、無視されたとか、まともに扱ってもらえなかったという訴えだ。
具体的なミスと訴訟に関連性がないとすれば、患者が受けた印象に合理性はない。しかし別の見方をすれば、医師-患者という人間関係において「軽んじられる」ことは患者側のリスク要因となる。だから医学的合理性を欠いてはいるが、社会的な意味合いはあるのかもしれない。
それにしても驚きだ。訴訟が「好き嫌い」のレベルで行われているというのだから。
だとしたら、訴えられる可能性を知るのに手術がうまいか下手かを調べても意味がない。医者と患者の関係さえわかればよいのだ。
医療について研究しているウェンディ・レビンソンは医者と患者の会話を何百件も録音した。ほぼ半数以上の医者は訴えられたことがない。あとの半数は二度以上訴えられている。レビンソンは彼らの会話だけを頼りに、二つのグループの医者に明らかな違いがあることを見つけた。
訴えられたことのない外科医は、訴えられたことのある外科医よりも、一人の患者につきあう時間が3分以上長かったのだ(前者が18.3分に対して後者は15分)。
更に補強されたよ(笑)。何だか、ますます民主主義が信用できなくなってきたな。大衆とはポピュリズムの異名だ。
判断材料は外科医の声を分析した結果だけ。それで十分、威圧感のある声の外科医は訴えられやすく、声が威圧的でなく患者を気遣うような感じの外科医は訴えられにくかった。これ以上【薄い】輪切りがあるだろうか?
困ったね。何を隠そう私は昔から威圧的な口調で有名なのだ(笑)。その上口が悪い。態度も横柄だ。そのうち誰かから訴えられることだろう。
他にもウォーレン・ハーディングは見栄えがよかったおかげで、第29代アメリカ大統領になれたという話も出てくる。ま、詐欺師ってえのあ、大体感じがいいからね。
私は直感的なタイプだ。そして気が短い。時折、「どうしてそんなに怒っているのかわからない」と言われる。説明すると相手は納得するのだが、「そんなことを一々説明させるな!」とまた怒る羽目になる。
会って話をすれば、かなりのことがわかる。メールやツイッターでも結構わかる。「小野さんと話していると、自分が丸裸にされるようで怖い」と言われたこともある。
私は昔から違和感を言葉にする努力を自らに課してきた。もちろん時間が掛かった場合もあるが、大体は言葉で説明できる。
顔色や目つき、声の抑揚、身のこなし方などから伝わってくる情報は意外と多いものだ。クルマに詳しい人であれば、必ずエンジン音に耳を傾けている。
でも直観を鍛えるのは難しい。だから感情や本能を磨くことを心掛けたい。具体的には感受性である。道を歩きながら光を感じているか。走り出した時の風を感じているか。木を見た時に根の存在を感じているか。二度と見ることのない雲の形に不思議を見出しているか。そんなことが大切なのだろう。

・『急に売れ始めるにはワケがある ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則』(旧題『ティッピング・ポイント』)マルコム・グラッドウェル
・災害に直面すると人々の動きは緩慢になる/『生き残る判断 生き残れない行動 大災害・テロの生存者たちの証言で判明』アマンダ・リプリー