定年
ある日
会社がいった。
「あしたからこなくていいよ」
人間は黙っていた。
人間には人間のことばしかなかったから。
会社の耳には
会社のことばしか通じなかったから。
人間はつぶやいた。
「そんなこといって!
もう四十年も働いて来たんですよ」
人間の耳は
会社のことばをよく聞き分けてきたから。
会社が次にいうことばを知っていたから。
「あきらめるしかないな」
人間はボソボソつぶやいた。
たしかに
はいった時から
相手は会社、だった。
人間なんていやしなかった。
【『石垣りん詩集』石垣りん(ハルキ文庫、1998年)】
2011-07-27
人間なんていやしなかった
2011-07-26
比較があるところには必ず恐怖がある/『恐怖なしに生きる』J・クリシュナムルティ
生存のために情動が機能しているとすれば、それは恐怖や不安に基づいている。生き延びる確率を上げる具体的な行動は「逃げる」ことだ。
グッピーを、コクチバスと出会わせたときの反応によって、すぐ隠れる個体を「臆病」、泳いで去る個体を「普通」、やってきた相手を見つめる個体を「大胆」と、三つのグループに分ける。それぞれのグループのグッピーたちをバスと一緒に水槽に入れて放置しておく。60時間ののち、「臆病」なグッピーたちの40パーセントと「普通」なグッピーたちの15パーセントは生存していたが、「大胆」なグッピーは1匹も残っていなかった。
【『病気はなぜ、あるのか 進化医学による新しい理解』ランドルフ・M・ネシー&ジョージ・C・ウィリアムズ:長谷川眞理子、長谷川寿一、青木千里訳(新曜社、2001年)】
リスクが高い環境では勇気が裏目に出る。臆病な方が優位なのだ。
グッピーですらタイプが分かれるわけだから、恐怖が本能に由来するのか学習で獲得されるのかは意見が真っ二つになっている。いずれにせよ、脳の深部(大脳辺縁系)に刻印されるのは間違いないだろう。
ヘビを見た瞬間、我々の身体は凍りつく。そして全ての感覚の注意がヘビに向けられる。思考が入り込む余地はない。これは健全な恐怖といえよう。
一方、コミュニティの政治化や高度情報化に伴って生まれる心理的な恐怖がある。クリシュナムルティが問題にしているのはこれだ。孤独は山林の静けさの中にあるのではない。むしろ都会の喧騒の中にある。
比較をされる中に落伍の恐怖がある。所有をすることで失う恐怖が生じる。政治の舵取りを誤ると雇用や医療の不安が生まれる。本来であれば喜ぶべき出産においても、現代社会は何らかの不安がつきまとう。
メディアとは他人の眼をカメラに据えたものだ。我々の振る舞いは周囲から「どう見られるか」に重きを置く。人格よりもどこに所属しているかで人を判断する。人間性よりも収入に注目する。
ヒエラルキーの競争力学を支えているのも恐怖だ。親は我が子が学校からドロップアウトすることを極度に恐れる。一度押された烙印は消えないからだ。村のルールに従わない者は村八分にされるのが我が国の伝統である。
では恐怖とはなんでしょう。恐怖をもたらす要因とはなんなのでしょう。やがて大河となるたくさんの細流や小川――恐怖をもたらす細流とは何か。そこには恐怖の凄まじい活力の源があるのです。
恐怖のひとつの原因は比較でしょうか。つまり自分をだれかと比べるということですか。
そのとおりです。ではあなたは、自分をだれとも比較しないで生きることはできるでしょうか。私の言っていることがおわかりですか。
イデオロギーのうえでも、心理的にも、また肉体的にさえも、自分をだれかと比べるとき、そこには相手のようになろうとする懸命な努力があり、そしてそうはなれないかもしれないという恐怖があるのです。実現したいという願望があるのに、実現できないかもしれない。――比較があるところにはかならず恐怖があるのです。
ではたずねます。人はなんらかの理想や価値観に近づこうとして、美醜、公正・不正などといった比較に囚われるわけですが、そうした比較をいっさいせずに生きていくことはできるでしょうか。現実には絶えることのない比較がつづいています。それで私たちはたずねているのです。比較が恐怖の原因なのか、と。
明らかにそうなのです。そして比較があるところには決まって追随があり、模倣があります。ですから比較や追随や模倣が恐怖の有力な原因だといえるわけです。いったい人は心理的に、比較や模倣や追随などせずに生きることができるのでしょうか。
もちろんできます。もしこれらが恐怖の有力な原因であるなら、そしてあなたが恐怖の終焉にとりくむなら、内的には比較はなくなります。何かになろうとしなくなるのです。比較とは、より良く、より高く、より高貴に思える何かになろうとすることにほかなりません。したがって比較とは、何かに「なろうとする」ことなのです。これは恐怖の要因のひとつでしょうか。ご自分で見いだしてください。
【『恐怖なしに生きる』J・クリシュナムルティ:有為エンジェル〈うい・えんじぇる〉訳(平河出版社、1997年)以下同】
「比較があるところにはかならず恐怖がある」という指摘が重い。何かになろうとすること自体が、自分を鋳型にはめ込む営みである。
・理想を否定せよ/『クリシュナムルティの教育・人生論 心理的アウトサイダーとしての新しい人間の可能性』大野純一
・努力と理想の否定/『自由とは何か』J・クリシュナムルティ
私たちはたいてい社会的地位を確保することで満足を得ようとしています。自分が無名の人間のままで終わることを恐れるからです。立派な地位にある人はきわめて丁重にあつかわれ、一方、地位をもたない人は粗末にあつかわれるように社会は作られています。それでだれもが、社会的地位や家庭内の地位を欲し、あるいは神の右手に座する地位を求めるわけです。でもこの地位は周囲によって認められるべきもの、そうでないと、それは決して地位とはいえないからです。私たちはいつも高いところに坐っていたい。内面では惨めさや苦悩が渦巻いているだけに、外では偉い人物として尊重されることがなんとも快いからです。このように、なんらかの形で傑出していると社会に認められようとして地位や威信や権力を渇望することは、言い換えれば他人を支配したいという願望にほかならず、この支配欲が攻撃性の一形態なのです。聖者はその気高さにふさわしい地位を求めますが、それはまるで鶏が農園で終始餌をつっつくのと同じくらい攻撃的だといえます。では何がこのような攻撃性を生みだすのか。それは恐怖心ではないでしょうか。
恐怖は人生の最大の課題のひとつです。恐怖に捕らえられた心は混乱と葛藤に陥るために、暴力的になったり、歪められたり、攻撃的になったりするのです。そうした心には自身の思考形態から離れる勇気がありません。これが偽善を生みだす原因なのです。恐怖から解放されるまでは、たとえ最高峰に登り、あらゆる種類の神を考えだそうとも、私たちは無知の闇をさまようだけでしょう。
たとえば私たちの受けている競争を土台とした教育、これもまた恐怖を引き起こします。堕落した愚かな社会の中ではだれもがみな、なんらかの恐怖にさいなまれながら日々を送っています。恐怖は、私たちの暮らしをねじ曲げ歪め退屈なものにしてしまう、恐るべき存在なのです。
ひとかどの者に「なろう」とする努力、ここに恐怖の本質があったのだ。よく考えてみよう。成功した企業の周りには失敗した企業が存在する。マーケットシェアを奪い合っているのだから当然だ。資本主義経済における利益は、消費者が支払う対価以外にも損失が発生するということだ。獲得競争は奪い合いを意味する。
国家は国民から奪い、企業は社員から奪い、学校は生徒から奪い、親は子から奪っている。金を、時間を、人生を。
失敗してみたらどうですか。発見してみたらどうでしょう。ところが恐れている人はいつも「正しいことをしなくては。人から立派に見れらなくては。あいつは何者だとか、とるにたりないやつだなんて世間からばかにされてはならない」などと考えるのです。そういう人は実際、根底から怯えきっているのです。野心的な人間とは、ほんとうは怯えている人のことです。そして怯えるているものには、愛や思いやりもありません。それはまるでびくびくと家の中に閉じこもっているようなものです。
我々は失敗を恐れる。だからこそ失敗することには意味があるのだろう。
以前こう書いたことがある。「今直ぐにできる世の中を変える方法:1.新聞の購読をやめる、2.テレビを消す、3.預金を全額下ろす――これだけで革命に等しい状況に陥る」(2010-12-23)。
この国に欠如しているのは流動性だ。
・日本は流動性なきタコツボ社会/『生物と無生物のあいだ』福岡伸一
そこで一つ妙案を思いついた。日本を一瞬で変えることが可能だ。それは「全国民が転職をすること」である。「この景気が悪い時にそんな与太話に耳を貸すものか」という声が聞こえてきそうだ。ごもっとも。しかし不況であるからこそ求人は買い手側(企業側)が強気になる。こうした構造をひっくり返すためには、労働者を大切にしない会社から去るのが手っ取り早い。利権にしがみつく連中もあっという間に一掃できるだろう。
みんなで思い切って、1年働いて3ヶ月休むことにしようぜ(笑)。そうすれば政治情況だって劇的に変わるはずだ。
安全への願望が我々を不自由にしている根本原因だ。大なり小なりリスクを引き受けた方が人生は面白い。自分に賭けろ。
・「私は正しい」と思うから怒る/『怒らないこと 役立つ初期仏教法話1』アルボムッレ・スマナサーラ
・死の恐怖/『ちくま哲学の森 1 生きる技術』鶴見俊輔、森毅、井上ひさし、安野光雅、池内紀編
・恐怖心をコントロールする/『ストレス、パニックを消す! 最強の呼吸法 システマ・ブリージング』北川貴英
・競争と搾取/『ブッダの真理のことば 感興のことば』中村元
・ブッダは論争を禁じた/『ブッダのことば スッタニパータ』中村元訳
色彩のマンダラ アフリカン・アート
今読んでいる本(『集合知の力、衆愚の罠 人と組織にとって最もすばらしいことは何か』)の表紙が気になったので調べてみた。荒々しいタッチと強調した直線で、頭上に物を載せて整然と歩くアフリカの女たちが描かれている。
あちこち飛んでいるうちに次々とアフリカのアーティストを発見。気に入ったものを紹介しよう。
私はロバート・ハインデルの絵が好きなのだが、ディビッド・キゴゼィのタッチは驚くほどよく似ている。
・AfricArt Design
・Ivuka Arts
愚行権
人間には、愚行権があります。それは、他人が考えると愚かな行為に見えても、自分がやりたいと思うことを行う権利です。
【『インテリジェンス人生相談 個人編』佐藤優〈さとう・まさる〉(扶桑社、2009年)】
2011-07-25
さようならの語源/『遠い朝の本たち』須賀敦子
人物評価は難しい。自分の価値観や体験に照らして相手を判断するわけだが、実際は好き嫌いにとらわれているだけのような気もする。感情の後ろを理屈が追いかけている節がある。脳内では大脳辺縁系にスイッチが入った後で前頭葉が作動しているに違いない。根拠や理由というものは後出しジャンケンなのだ。
アン・モロー・リンドバーグはチャールズ・リンドバーグの夫人である。大西洋単独無着陸飛行(1927年)を成し遂げた、あのリンドバーグだ。
リンドバーグはヒトラーを「疑いなく偉大な人物」とたたえた。これにこたえて、ナチス・ドイツは1936、38、39年の3回リンドバーグを招いた。リンドバーグは、ドイツ空軍を視察して、その能力を高く評価した。
多くのアメリカ人は、
「リンドバーグはナチのシンパ」
と思っていた。
【『秘密のファイル CIAの対日工作』春名幹男(共同通信社、2000年/新潮文庫、2003年)】
この件(くだり)を読んだ私は、リンドバーグを唾棄すべき人物と認定した。ところが数年後、菅原出〈すがわら・いずる〉によって蒙(もう)を啓(ひら)かれた。
・アメリカ経済界はファシズムを支持した/『アメリカはなぜヒトラーを必要としたのか』菅原出
リンドバーグはただ自分に忠実な男であったのかもしれない。
アン・モローは駐メキシコ大使の子女で、その文章からは鋭敏な感受性と聡明さが窺える。リンドバーグ夫妻は1931年に調査飛行で来日している。
千島列島の海辺の葦の中で救出されたあと、リンドバーグ夫妻は東京で熱烈な歓迎をうけるが、いよいよ船で(どうして飛行機ではなかったのだろう。岸壁についた船とその船と送りに出た人たちをつなぐ無数のテープをえがいた挿絵をみた記憶があるのだが)横浜から出発するというとき、アン・リンドバーグは横浜の埠頭をぎっしり埋める見送りの人たちかが口々に甲高く叫ぶ、さようなら、という言葉の意味を知って、あたらしい感動につつまれる。
「さようなら、とこの国々の人々が別れにさいして口にのぼせる言葉は、もともと「そうならねばならぬのなら」という意味だとそのとき私は教えられた。「そうならねばならぬのなら」。なんという美しいあきらめの表現だろう。西洋の伝統のなかでは、多かれ少なかれ、神が別れの周辺にいて人々をまもっている。英語のグッドバイは、神がなんじとともにあれ、だろうし、フランス語のアディユも、神のもとでの再会を期している。それなのに、この国の人々は、別れにのぞんで、そうならねばならぬのなら、とあきらめの言葉を口にするのだ」(※ 『翼よ、北に』アン・モロー・リンドバーグ著)
【『遠い朝の本たち』須賀敦子(筑摩書房、1998年/ちくま文庫、2001年)】
露のはかなさを思い、散る桜を愛でるのと同じメンタリティか。鮮やかな四季の冬が死の覚悟を促しているのか。潔さ、清らかさが日本人全体の自我を形成している。移ろいゆく時、墨絵の濃淡を味わうのが我々の流儀だ。谷崎は陰影を礼讃した。
のっとるべき理(ことわり)を法(のり)という。水(さんずい)が去ると書いて法。そこに循環する未来は映っていない。ただこの一瞬を味わいつつ惜しむ達観が諦観へと通じる。
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世の中にある人と、栖(すみか)とまたかくのごとし。(『方丈記』鴨長明)
・リンドバーグ愛児誘拐事件(アガサ・クリスティの小説『オリエント急行の殺人』の序盤で登場する誘拐事件は本事件を参考にしているとされる)
財(グッズ)と良いもの(グッド)
財(グッズ)は必ずしも良いもの(グッド)とは限らないし、良いものは必ずしも財ではない。夕日は、だれも対価を支払わないので、財ではない。シアン化物入りの痛み止めカプセル一瓶は、対価を払う人がいるので財になる。
【『ギャンブルトレーダー ポーカーで分かる相場と金融の心理学』アーロン・ブラウン:櫻井祐子訳(パンローリング、2008年)】
2011-07-24
ファイト新聞社
1冊読了。
49冊目『宮城県気仙沼発! ファイト新聞』ファイト新聞社(河出書房新社、2011年)/よくぞカラーにしてくれた。河出書房新社に心から敬意を表する。東日本大震災で最も被害の大きかった気仙沼市。その避難所に掲げられた壁新聞が「ファイト新聞」だ。小学生4人が誰に言われたわけでもなく自発的に発行した。初代編集長は吉田理紗さん(小2)。手紙を書くのが大好きな彼女は、「みなさんに元気になってほしい」と壁新聞の発行を思い立つ。3月18日から5月2日分までが収録されているが、この間、休刊日は4月30日だけだ。毎号、4コマ漫画を掲載している。この子らのマジックに込めた力に思いを馳せる。彼女たちが発信するメッセージは復興の槌音(つちおと)となって響き渡る。
悪(evill)は生きる(live)の逆綴り
8歳の子供特有のものの見方で、息子はこう語っている。「変だね、お父さん。悪(evill)っていう字のつづりは、生きる(live)っていう字のつづりと逆になっているんだね」。たしかに、悪は生に対置(たいち)されるものである。生命の力を阻(はば)むものが悪である。簡単に言うならば、悪は殺すことと関係がある。具体的には、悪は殺りく――つまり、不必要な殺し、生物的生存に必要のない殺しを行うことと関係している。
悪は殺しと関係があると言ったが、これは肉体的な殺しだけを言っているのではない。悪は精神を殺すものでもある。
【『平気でうそをつく人たち 虚偽と邪悪の心理学』M・スコット・ペック:森英明訳(草思社、1996年)】
・愛(amor)はローマ(Roma)の逆綴り
人生という名の番組、私という受信機/『脳のなかの幽霊』V・S・ラマチャンドラン
地デジ化がいいねと言った総務省 7.24はアナログ命日
サラダ記念日の韻を踏もうと試みたのだが見事に失敗した。7.24は「ナナニーヨン」と詠んでくれ給え。
我が家のアナログテレビ死去に伴い、「テレビはアナクロ(時代錯誤)だ」という信念はいや増して高くそびえる。私は10代後半からテレビを殆ど視聴しなくなり、ここ数年は年に一度くらいしか見ていない。それゆえ普段はコンセントを外したままだ。
アナログテレビは本当に死んだのだろうか? 毎日jp(7月24日)によれば、「24日正午からは番組終了や問い合わせ先などを表示する「お知らせ画面」に切り替わった。25日午前0時までにはアナログ電波の送信そのものが止まり、砂嵐のような画面になる」とのことだ。すると脳死ってわけだな。
送信が止まれば受信する情報は存在しない。ここが重要なのだが、情報を遮断されることは機能喪失を意味する。つまり送信停止=受信不能なのだ。以下、不遜な例えを連発するがご容赦願いたい。真っ暗闇の世界に置かれた人と、明るい世界で生きる視覚障害者は内実において一致する。周囲の人々全員がわけのわからぬことを言い始める状況と、重度の認知症を患う人も同様だ。世界全体が狂気に包まれれば、あなたが異常と診断されるわけだ。
情報の相対性はツーウェイの一方が機能しなくなることでコミュニケーションが喪失する。
あなたがテレビ番組の『ペイウォッチ』を見ているとする。さて『ペイウォッチ』はどこに局在しているのだろうか? テレビの画面で光っている燐光体のなかにあるのか、ブラウン管のなかを走っている電子のなかにあるのか。それとも番組を放送しているスタジオの映画用フィルムやビデオテープのなかだろうか。あるいは俳優にむけられたカメラのなかか?
たいていの人は即座にこれが無意味な質問であると気づくだろう。もしかすると、『ペイウォッチ』はどこか一カ所に局在しているのではなく(すなわち『ペイウォッチ』の「モジュール」というものは存在せず)、全宇宙に浸透しているのだという結論をだしたくなった人もいるかもしれない。だがそれもばかげている。それは月や、私の飼い猫や、私が座っているソファには局在していないからだ(電磁波の一部がこれらに到達することはあるかもしれないが)。燐光体やブラウン管や電磁波やフィルムやテープは、どれもみなあきらかに、月や椅子や私の猫にくらべれば、私たちが『ペイウォッチ』と呼んでいるシナリオに直接的な関係がある。
この例から、テレビ番組がどんなものかを理解すれば、「局在性か非局在性か」という疑問が力を失い、それに代わって「どういう仕組みになっているのか」という疑問がでてくるのがわかる。
【『脳のなかの幽霊』V・S・ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー:山下篤子訳(角川書店、1999年/角川文庫、2011年)】
朗報だ。12年も経ってやっと文庫化された。テレビ番組を通した問いかけは仏教の属性論と規を一にしている。
・「私」とは属性なのか?~空の思想と唯名論/『空の思想史 原始仏教から日本近代へ』立川武蔵
番組を人生に置き換えてみよう。私の人生はどこにあるか? 家族や友人の視線の中か、私の感覚か、それとも記憶か、あるいは写真か?
「局在性か非局在性か」との指摘は存在論を鋭く抉(えぐ)り、実は関係性という双方向性の中で人生が成り立っていることを明らかにしている。ラマチャンドランは縁起(えんぎ)を志向している。
テレビが私であるとすれば、自我を形成するのが番組と考えてよかろう。幼い頃はテレビの操作法を知らないから、親が見る番組の影響を受ける。思春期になると自分の嗜好(しこう)が形成されてゆく。何らかの信念をもつ人は最終的に一つの番組しか見ない。スポーツ、バラエティ、歌番組、ニュース、ルポ、そして政治、思想・哲学、宗教へと至る。
・宗教OS論の覚え書き
1963年から始まった「私」という番組はいつの日か終わりを迎える。受信機としての機能も失う。「昔、シャボン玉ホリデーという番組があったよな?」あったあった。「あれは面白い番組だったよな」確かに影響力があった。「昔、小野って野郎がいたよな?」いたいた――ってな具合だ。
もしも「私」が生まれ変わるとすれば、それは「私」という情報に依存している以上、再放送とならざるを得ない。つまり再生はあっても新生はない。来世を信じる人は六道輪廻を望んでいることになる。自我の延長戦、繰り返し観る映画、因果は巡る糸車、ネズミ車のハムスターってわけだよ。
自我への執着をブッダは諸法無我で木っ端微塵にした。空の概念をわかりやすくいえば、「存在は電波である」となる。電波野郎って意味じゃないからね(笑)。送信と受信の関係性の中で存在し、時を経て宇宙に溶け込む。
「これあればかれあり、これ生ずるが故にかれ生ず、これなければかれなし、これ滅するが故にかれ滅す」(雑阿含経)。
この世界に単独で存在するものは何ひとつない。西洋近代の扉を開いたのはデカルトだ。「我思う、ゆえに我あり」と彼が自覚した瞬間に、人間の自我は分断されたものとなった。
・社会を構成しているのは「神と向き合う個人」/『翻訳語成立事情』柳父章
西洋の分断された自我が世界の分断を生んだ。平和に暮らしていたアフリカの黒人は奴隷とされ、友好的なアメリカ先住民は虐殺された。世界というテレビでは近代以降、キリスト教の番組が席巻している。宣教という名目で信仰をも支配しようと目論んでいる。彼らはチャンネル権争いのためとあらば戦争までやってのける。
キリスト教に鉄槌を下さずしてポストモダンは成立しない。そして既成概念を打ち破らなければ自由を享受することは不可能だ。
今まで通りテレビを見ない自由は確保しようと思う。
・先入観を打ち破る若き力/『脳のなかの幽霊』V・S・ラマチャンドラン
全能の逆説
【基本的な問い】全能者は自ら全能であることを制限し、全能でない存在になることができるか?
【古典的な問い】全能者は〈重すぎて何者にも持ち上げられない石〉を作ることができるか?
この問いは次のように分析できる。(哲学者の回答)
1.ある存在は、〈それ自身が持ち上げることのできない石〉を作ることができるか、できないかのどちらかである。
2.もし、その存在が〈それ自身が持ち上げることのできない石〉を作ることができるならば、その存在は全能ではない。
3.もし、その存在が〈それ自身が持ち上げることのできない石〉を作ることができないならば、その存在は全能ではない。
次のような要請によって逆説を解消しようという立場もありうる。即ち、全能性は、常に全てのことができることを必ずしも要求しない、という要請である。そうすれば、次のように理屈をつけられる。
1.その存在は、作った時点では持ち上げられない石を作ることができる。
2.しかし、その存在は全能であるから、その存在は後からいつでも、持ち上げられる程度に石を軽くすることができる。従って、その存在を全能であるというのは尚も合理的である。
思慮深いスティーヴン・ホーキングによる創造主と自然法則との関係についての考察に従い、古典的記述法を次のように直すことができるだろう。
1.全能者がアリストテレスの物理学に従う宇宙を創造する。
2.その宇宙で、全能者は自分自身が持ち上げられないほど重い石を作ることができるであろうか。
存在が偶発的に全能である場合は逆説は解消できる。
1.全能者は自分に持ち上げられない石(あるいは分割できない原子など)を作る。
2.全能者はその石を持ち上げられず、全能でない者になる。
存在が本質的に全能である場合は逆説は解消できる。
1.その全能者は本質的に全能である、故に全能でない者になることはできない。
2.さらに、全能者は論理的に不可能なことをすることはできない。
全能者が持ち上げられない石を創造することは、上記の論理的不可能性にあたる。故に全能者がそのようなことを要求されることはない。
3.全能者はそのような石を創造することはできないが、それでも尚全能性を保つ。
一部の哲学者は、全能性の定義にデカルトの観点を含めればこの逆説は解消するという姿勢を崩していない。その観点とは全能者は論理的に不可能なことをなし得るというものである。
1.全能者は論理的に不可能なことをすることができる。
2.全能者は自らが持ち上げられない石を作ることができる。
3.全能者は次いでその石を持ち上げる。
以上、Wikipediaより。
2011-07-23
愛(amor)はローマ(Roma)の逆綴り
ローマ・カトリック教会という聖なる権威と聖なる結婚の誓いとに違反することになってでも、愛において自分の意志を信じるというエロイーズの考え方には、ルネッサンスの最初の光明が見てとれる。つまりは、愛(amor)はローマ(Roma)と逆綴りなのである。
【『エロスと精気(エネルギー) 性愛術指南』ジェイムズ・M・パウエル:浅野敏夫訳(法政大学出版局、1994年)】
・悪(evill)は生きる(live)の逆綴り
死刑と殺戮の覚え書き
米国で20年ぶり死刑執行をビデオ撮影、残虐性検証のため
米ジョージア(Georgia)州で21日夜、死刑囚の刑の執行が約20年ぶりにビデオ録画された。
地元メディアによると、両親と妹を殺害したとして有罪となったアンドルー・デヤング(Andrew Grant DeYoung)死刑囚は、現地時間午後8時4分(日本時間22日午前9時4分)に薬物注射による刑を執行された。
ビデオ撮影を求めたのは、やはり同州で死刑判決を受けたグレゴリー・ウォーカー(Gregory Walker)死刑囚の弁護団。
米国の一部の州では、死刑執行に使用する薬物として、入手が困難なチオペンタールナトリウムの代わりに、動物の安楽死に使われるペントバルビタールの使用を認めている。しかし、ペントバルビタールの使用には残虐だとの批判があり、ウォーカー死刑囚の弁護団は残虐性の検証のため撮影を要請し、州最高裁の許可を得ていた。
米死刑情報センター(Death Penalty Information Center)代表は、「死刑執行の際に何が起きているのか、公開される情報は非常に限られている。ビデオ撮影によって、一般の人も何らかの知識が得られると思う」と語っている。
【AFP 2011-07-22】
米国の死刑、執行失敗例では中世並みの悶絶
※この記事はショッキングな表現を含んでいますのでご注意ください
米国の死刑といえば、医学処置による人道面にも配慮したものだと思われているが、ときに中世の拷問とも違わぬ陰惨な最期を悶絶しながら遂げる死刑囚もいる。
絶叫、体が焦げる匂い、あまりの残酷さに立会人たちは気絶する……「犬猫の殺処分のほうがもっと人道的です」。1992年にアリゾナ(Arizona)州で死刑に立ち会った記者カーラ・マックレーン(Carla McClain)は語った。このとき刑を執行されたドナルド・ユージーン・ハーディング(Donald Eugene Harding)死刑囚は、ガス室のなかで死ぬまで10分以上、のたうちまわり、もがき苦しんだ。
◆針刺し18回、2時間かけても注射できず
9月、ローメル・ブラウン(Romell Brown)死刑囚の刑執行では、致死薬注射が試みられたが、針を刺すのに連続18回失敗し、ブラウン死刑囚は執行室から生還した米史上2番目の死刑囚となった。執行官らが2時間かけてもうまく注射できず、オハイオ(Ohio)州当局が執行中止を命じたのだった。
過去25年間、米国で死刑に処された者のうち、執行の失敗で苦しんだ者は少なくない。肉を焦がされた者、血でシャツが真っ赤に染まった者。立ち会った人びとが、苦悶する死刑囚を目撃することもしばしばだ。
1999年、フロリダ(Florida)州最高裁のリーンダー・ショー(Leander Shaw)判事は、電気椅子で処刑されたアレン・リー・デービス(Allen Lee Davis)死刑囚の写真を見ておののき、「そのカラー写真には、どこから見ても、フロリダ州民に残酷な拷問を受け、死に至った男の姿が映っていた」と書いた。
デービス死刑囚は、約160キロの彼の体躯(たいく)にあわせてしつらえられた特製の電気椅子にくくりつけられていた。処刑が執行され死を宣告されるまでに、口からあふれ出した血が白いシャツにぐっしょりとこぼれ、電気椅子に彼を縛り付けていたストラップのバックルの穴からもしたたっていた。
◆電気椅子ではなく火あぶり? ガス室の執行官は酔っ払い
コロラド大学のマイケル・ラデレット(Michael Radelet)教授は、米死刑情報センター(Death Penalty Information Center)と共同で、執行に立ち会いを求められた目撃者らから40件以上の失敗例に関する証言を集めた。
恐怖の失敗例は、現在米国で執行に使用されている一般的な方法、つまり電気椅子、薬剤注射、ガス殺のすべてに確認でき、そうした失敗のほとんどが人為的ミスによるものだった。
1983年にはアラバマ(Alabama)州で、電気椅子の発火事故があった。ジョン・エバンス(John Evans)死刑囚の足に取り付けられた電極が燃えあがったのだ。左のこめかみ近くに取り付けた電極もトラブルを生じ、顔を覆っていたフードの下から煙と火花がもれ出た。執行はやり直されたが、煙と体の焦げた匂いがたちこめるなか、エバンス死刑囚の心臓はまだ動いていた。3度目のスイッチが入れられたが、エバンス死刑囚がようやく息絶えたのは、それから14分後だった。
電気椅子による執行の失敗はその後も各地で続いた。
ガス殺では1983年ミシシッピ(Mississippi)州で、ジミー・リー・グレー(Jimmy Lee Gray)死刑囚が恐ろしくもだえ苦しんだため、当局が立会人室から人払いするほどだった。後に、グレー死刑囚の処刑の担当執行官は、酔っていたことを明らかにした。
◆死刑囚最後の言葉「これは処刑じゃない、殺人だ」
近年では薬剤注射は残酷だとして起こされている訴訟もいくつかあるが、全米の州では致死薬注射が最も一般的に使われており、最高裁も2008年に薬剤注射は合憲と判断している。
しかし、33分間を苦悶したベニー・デンプス(Bennie Demps)死刑囚にとって、薬剤注射による刑は激痛をともなった。執行官らが点滴注射が失敗した場合の予備にと別の静脈を探そうとしたのだ。デンプス死刑囚は最後の言葉で「わたしはここで切り刻まれた。ものすごい痛さだ。彼らはももに切り込みを入れ、足に切り込みを入れ、血は吹き出まくっている。こんなのは処刑じゃない。殺人だ」と言い遺した。
最近の失敗例のいくつかは、冒頭のブルーム死刑囚が処刑されたオハイオ州で起こっている。
「それじゃ、効かないよ! 効かないって」。ジョセフ・クラーク(Joseph Clark)死刑囚は2006年5月、執行官が22分かけて探し出した静脈が、注射が始まったとたんに破裂すると、すすり泣きながら叫んだ。
1年後も、オハイオ当局はクリストファー・ニュートン(Christopher Newton)死刑囚の静脈に針を刺すのに2時間かかった。あまりに長くかかったので、ニュートン死刑囚は途中でトイレ休憩を許可された。
米史上、死刑場から生きて戻った最初の人物は1940年代、ルイジアナ(Louisiana)州で電気椅子に座った若い黒人の男、ウィリー・フランシス(Willie Francis)死刑囚。彼は2度目、やり直された刑で死んだ。
【AFP 2009-10-18】
世界一残虐な国アメリカが自国民の人権や他国の動物に配慮をするのが何とも摩訶不思議。彼らが行ってきたことを振り返ってみる必要がある。
猟奇殺人を犯した大半はベトナム帰りの米兵だと思われる。
・米兵は拷問、惨殺、虐殺の限りを尽くした/『人間の崩壊 ベトナム米兵の証言』マーク・レーン
・魔女は生木でゆっくりと焼かれた/『魔女狩り』森島恒雄
・『奴隷とは』ジュリアス・レスター
家畜文化が奴隷を生んだ。
・動物文明と植物文明という世界史の構図/『環境と文明の世界史 人類史20万年の興亡を環境史から学ぶ』石弘之、安田喜憲、湯浅赳男
・環境帝国主義の本家アメリカは国内法で外国を制裁する/『動物保護運動の虚像 その源流と真の狙い』梅崎義人
・米軍による原爆投下は人体実験だった/『洗脳支配 日本人に富を貢がせるマインドコントロールのすべて』苫米地英人
人間は考える葦である。では何を考えるのか? 神の存在と神の意志だ。これを彼らは理性と名づけた。つまり、彼らの神を信じない者=異教徒は人間として認められないことになる。
古来、西洋ではヨーロッパの外側には化け物が棲んでいると考えられていた。
・コロンブスによる「人間」の発見/『聖書vs.世界史 キリスト教的歴史観とは何か』岡崎勝世
アフリカで黒人と遭遇し、アメリカで先住民を見つけたヨーロッパ人はヴァチカンに手紙で問い合わせた。「彼らは人間なんでしょうか?」と。回答は「ノー」であった。異教徒を殺戮するのは彼らにとって正義である。ヨシュア記で「殺せ」と命じられているからだ。
映画『猿の惑星』の猿は日本人に模していたという。それは単なる暗喩の類いではない。
・「欧米人が仕掛ける罠」武田邦彦、高山正之
キリスト教における神と人間の絶対的な差別が、神の僕と異教徒の間に差別を形成している。我々が蝿や蚊を平然と殺すように、彼らは有色人種を殺戮してきた。白人は同じ人間だから殺すのはまずいよな、という認識でつくられたのがEUである。
・Executions 1995
2011-07-22
ラマヌジャンの『ノート』
ラマヌジャンの(※『ノート』の)結果には誤まっているものがままあった。また、彼が期待したほどの深みはないものもあったし、西欧の数学者によって50年、100年、いや200年も前に発見されていたことを知らずに再発見していたのにすぎないものもあった。しかし、その多く――ハーディのみたところ約3分の1、後の数学者の評価によれば3分の2――は、息詰まるほどの新奇性に満ちたものであった。ハーディは知った。ラマヌジャンから送られた厚い、数式だらけの手紙は、この10年にわたって『ノート』に蓄積されてきたもののごくごく一部、そう、氷山の一角にすぎなかったのだ、と。3000、いや、4000もの定理、系、例題が証明や解説のほとんどないままにページからページへ行進してゆく。まるで枝葉を切りとった人生訓のように、一行か二行の数式に数学的真実が秘められているのだ。
【『無限の天才 夭逝の数学者・ラマヌジャン』ロバート・カニーゲル:田中靖夫訳(工作舎、1994年)】
・ラマヌジャンの『ノート』
・シュリニヴァーサ・ラマヌジャン
2011-07-21
意識は膨大な情報を切り捨て、知覚は0.5秒遅れる/『ユーザーイリュージョン 意識という幻想』トール・ノーレットランダーシュ
・『神々の沈黙 意識の誕生と文明の興亡』ジュリアン・ジェインズ
・ユーザーイリュージョンとは
・エントロピーを解明したボルツマン
・ポーカーにおける確率とエントロピー
・嘘つきのパラドックスとゲーデルの不完全性定理
・対話とはイマジネーションの共有
・論理ではなく無意識が行動を支えている
・外情報
・論理の限界
・意識は膨大な情報を切り捨て、知覚は0.5秒遅れる
・神経系は閉回路
・『身体感覚で『論語』を読みなおす。 古代中国の文字から』安田登
・『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』ユヴァル・ノア・ハラリ
・『ポスト・ヒューマン誕生 コンピュータが人類の知性を超えるとき』レイ・カーツワイル
・意識と肉体を切り離して考えることで、人と社会は進化する!?【川上量生×堀江貴文】
・『AIは人類を駆逐するのか? 自律(オートノミー)世界の到来』太田裕朗
・『奇跡の脳 脳科学者の脳が壊れたとき』ジル・ボルト・テイラー
・『あなたの知らない脳 意識は傍観者である』デイヴィッド・イーグルマン
・『リアリティ+ バーチャル世界をめぐる哲学の挑戦』デイヴィッド・J・チャーマーズ
・必読書 その五
1990年、アメリカ連邦議会は「脳の10年」を採択した。ゲノムプロジェクトも同年開始。10年後にはほぼ全ての遺伝子配列が明らかになった。計画は予想よりも短期間で成し遂げられた。コンピュータ技術が劇的に進化したためだ。
脳が作ったコンピュータが脳を解明するというのだから面白い。デジタル化によってコンピュータは並列処理を行えるようになった。計算機は一足飛びで脳に近づいた。
脳科学は飛躍した。だが、「なぜ意識があるのか?」はまだわかっていない。そもそも「意識とは何か」も不明のままだ。「私」という現象を支えているのは意識の反応であり、それをパターン化したものが「自我」だ。
世界は五感で構成されている。世界は「在る」のではない。ただ世界を「感じて」いるだけだ。世界は快不快、喜怒哀楽、幸不幸によって異なる。人の数だけ世界があると考えてよかろう。
では脳は何を感受し、意識を発動するのか?
物質系や生命系の世界の複雑さは、「深さ」、つまり処分された情報量として記述できる。最大の情報量を持つもの、それゆえに最長の記述を要するようなものには、私たちは関心を抱かない。それは、無秩序や乱雑さや混沌と同じだからだ。また、あまりに規則正しく先の読めるものにも心を引かれない。そこにはなんの驚きもないからだ。
私たちの興味をそそるのは、歴史を持つもの、つまり、閉じて動かぬことによってではなく、外界と相互作用を行ない、途中で大量の情報を処分することによって長い間、存続してきたものだ。だから、複雑さや深さは、〈熱力学深度〉(処分された情報の量)またはそれと密接に関連した〈論理深度〉(情報の処分に要した計算時間)で測定できる。
会話には情報交換が伴う。しかし、そのこと自体が重要なのではない。交わされる言葉にはわずかな情報しか含まれていない。肝心なのは、言葉になる前に行なわれる情報の処分だ。メッセージの送り手は大量の情報を圧縮し、情報量をごく小さくしてからそれを口にする。受け手はコンテクストから判断し、実際に処分された大量の情報を引き出す。こうして送り手は、情報を捨てることで〈外情報〉を作り出し、その結果生まれた情報を伝達し、相応量の〈外情報〉を受け手の頭によみがえらせることができる。
つまり、言語の帯域幅(毎秒伝達できるビット数)はいたって小さい。毎秒せいぜい50ビット程度だ。言語や思考で意識はいっぱいになるのだから、意識の容量が言語より大きいはずはない。1950年代に実施された一連の心理物理学実験から、意識の容量は非常に小さいことが判明した。毎秒40ビット以下、おそらくは16ビットを下回る。
感覚器官をを通じて取り込む情報量が毎秒約1100万ビットであることを思うと、この数字は桁外れに小さい。意識は、五感経由で間断なく入ってくる情報のほんの一部を経験するにすぎない。
とすれば、私たちの行動は、感覚器官を通して取り込まれながら意識には上らない大量の情報に基づいているはずだ。毎秒数ビットの意識だけでは、人間行動の多様性は説明できない。事実、心理学者は閾下知覚の存在を確認している。(ただし、このテーマに関する研究の歴史には奇妙な空白期間があり、その背景には、そうした研究から得られた知識が商業目的に悪用されることへの具体的懸念と、人間の得体の知れなさに対する獏とした恐れがあるようだ)。
【『ユーザーイリュージョン 意識という幻想』トール・ノーレットランダーシュ:柴田裕之訳(原書、1991年/紀伊國屋書店、2002年)以下同】
何と毎秒1100万ビットの情報量の99.99%を切り捨てていることになる。謡曲「求塚」(もとめづか/観阿弥作)に「されば人、一日一夜を経(ふ)るにだに、八億四千の思ひあり」とある。人は一日に八億四千万もの念慮を為すというのだ。この時代の億が10万であるとしても、84万ってことになりますな。ちなみに起きている時間を16時間として計算すると、1時間=52500、1秒=14.58という数字が導かれる。何となく16ビット以下に近づいているような気がする(笑)。
たぶん生存に関わらない情報は捨象(しゃしょう)されるのだろう。家が火事になった場合に求められるのは分析することではなく逃げることだ。そう考えると生きるためには、理性よりも情動を発揮する方が有利なのだろう。
・ソマティック・マーカー仮説/『デカルトの誤り 情動、理性、人間の脳』(『生存する脳 心と脳と身体の神秘』改題)アントニオ・R・ダマシオ
なお外情報とはトール・ノーレットランダーシュが命名した概念で、発した言葉に表されていない情報のこと。沈黙が雄弁と化す場合もある。人の心をつかむのも大抵の場合一言である。もっとわかりやすいのは音楽だ。言葉を介さずにメッセージを伝えるのだから。
膨大な情報を切り捨て、最小限の情報を知覚した脳は意識を発動させる。
結果に疑問の余地はなかった。〈準備電位〉が動作の0.55秒前に現れ始めたのに対し、意識が始動したのは行為の0.20秒前だった。したがって、決意の意識は〈準備電位〉の発生から0.35秒遅れて生じることになる。言い換えれば、脳の起動後0.35秒が経過してから、決意をする意識的経験が起きたわけだ。
数字を丸めれば(データの出所が明らかな場合はさしつかえなかろう)、自発的行為を実行しようという意図を意識するのは、脳がその決定を実行し始めてから0.5秒たった後という結論になる。
つまり、三つの事象が起きている。まず〈準備電位〉が発生し、ついで被験者が行為の開始を意識し、最後に行為が実行される。
これを読んだ時は腰を抜かした。だってそうだろ、意識する前に脳が動いている(準備電位)というのだから。するってえと、やっぱり自由意志はないものと考えられる。(何度でも紹介するぞ!)
・人間に自由意思はない/『脳はなにかと言い訳する 人は幸せになるようにできていた!?』池谷裕二
体の触覚に関連する脳領域に電気刺激を与えると、体に触れられた、という感覚が生まれる。人間には、皮質への刺激を感知する触覚がない。通常は頭蓋骨が刺激から脳を守っているからだ。脳への刺激はけっしてないのだから、それを感知する生物学的な意味がない。頭蓋が開かれているとしたら、ほかにもっと憂慮すべきことがあるわけで、感覚皮質への刺激で爪先がうずくかどうかなど考えていられない。
頭蓋骨はパンドラの匣(はこ)だったというわけだ。というよりは、むしろ脳が頭蓋骨から飛び出そうとしているのかもしれない。「こんな狭苦しいところに、いられるかってえんだ!」といった具合に。
意識とそれが基づく脳内の活動に関するリベットの研究は、大きく二つに分けられる。一つは、ファインスタインの患者に対する一連の実験であり、これが、意識が生じるまでには0.5秒の脳活動を要するという、驚くべき発見をもたらした。この研究の後に、さらに驚嘆すべき発見へとつながる。すなわち、意識は時間的な繰り上げ調整を行ない、その結果私たちは、外界からの刺激の自覚が、実際は刺激の0.5秒後に生じるにもかかわらず、あたかも刺激の直後に生じたかのように感じる。
・人間が認識しているのは0.5秒前の世界/『進化しすぎた脳 中高生と語る〔大脳生理学〕の最前線』池谷裕二
0.5秒遅れの情報を脳が補正している。凄いよね。現在という瞬間の中で過去と未来が目まぐるしく交錯しているのだから。
意識はその持ち主に、世界像と、その世界における能動的主体としての自己像を提示する。しかし、いずれの像も徹底的に編集されている。感覚像は大幅に編集されているため、意識が生じる約0.5秒前から、体のほかの部分がその感覚の影響を受けていることを、意識は知らない。意識は、閾下知覚もそれに対する反応も、すべて隠す。同様に、自らの行為について抱くイメージも歪められている。意識は、行為を始めているのが自分であるかのような顔をするが、実際は違う。現実には、意識が生じる前にすでに物事は始まっている。
意識は、時間という名の本の大胆な改竄(かいざん)を要求するイカサマ師だ。しかし、当然ながら、それでこそ意識の存在意義がある。大量の情報が処分され、ほんとうに重要なものだけが示されている。正常な意識にとっては、意識が生じる0.5秒前に〈準備電位〉が現れようが現れまいが、まったく関係ない。肝心なのは、何を決意したかや、何を皮膚に感じたか、だ。患者の頭蓋骨を開けたり、学生に指を曲げさせたりしたらどうなるかなど、どうでもいい。重要なのは、不要な情報をすべて処分したときに意識が生じるということだ。
「私」とはこれほどあやふやな存在なのだ。トール・ノーレットランダーシュは意識という幻想を「ユーザーイリュージョン」(利用者の錯覚)と名づけた。
世界が感覚で構成されている以上、我々の経験はシミュレーションとならざるを得ない。つまり脳が世界を規定するのだ。そして意識は「私」をでっち上げ、存在の重力を生み出す。
華厳経(けごんきょう)に「心は工(たくみ)なる画師(えし)の如く種種の五陰(五蘊)を画(えが)く。一切世間の中に法として造らざること無し」とある。仏教は脳科学だったのだ。
「世界も私も幻想だ」というのは簡単だ。それよりも一番大切なことは、生(せい)の川が刻々と流れている事実を知ることだ。この流動性をブッダは諸行無常と鋭く見抜き、「私」の実体は諸法無我であると喝破した。
世界と私は何と不思議に満ちていることか。

・デカルト劇場と認知科学/『神はなぜいるのか?』パスカル・ボイヤー
・視覚情報は“解釈”される/『人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか』ビル・ブライソン
・知覚系の原理は「濾過」/『唯脳論』養老孟司
・「私」という幻想/『悟り系で行こう 「私」が終わる時、「世界」が現れる』那智タケシ
・信じることと騙されること/『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』内山節
人間は人間にとって鏡なのである
人間は人間にとって鏡なのである。鏡というものは、物を光景(スペクタル)に、光景を物に変え、私を他人に、他人を私に変える万能魔術の道具なのだ。これまでもしばしば、画家たちは鏡について思いを凝らしてきた。それというのも、彼らは遠近法というトリックのばあいと同様に、鏡というこの「機械的トリック」のもとでも、〈見る者〉と〈見えるもの〉との転換を認めたからであり、そしてこの転換こそ、ほかならぬわれわれの肉体の定義であり、また画家の使命の定義なのである。
【『眼と精神』M・メルロ=ポンティ:滝浦静雄、木田元〈きだ・げん〉訳(みすず書房、1966年)】
2011-07-20
ギャンブラーの哲学/『福本伸行 人生を逆転する名言集 2 迷妄と矜持の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編
・『銀と金』福本伸行
・『賭博黙示録カイジ』福本伸行
・『福本伸行 人生を逆転する名言集 覚醒と不屈の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編
・ギャンブラーの哲学
・『無境界の人』森巣博
・『賭けるゆえに我あり』森巣博
・『真剣師 小池重明 “新宿の殺し屋"と呼ばれた将棋ギャンブラーの生涯』団鬼六
金を賭けるのがギャンブルなら、時間を賭けるのが人生といえるだろう。
「諸君は永久に生きられるかのように生きている」とセネカが糾弾している。生と死の理(ことわり)を思索することもなく、肝心なことは全部先送りにしながら我々は年老いてゆく。
今この瞬間も刻一刻と死が迫っているのに平然と構えているのはどうしたことか。なぜこれほど鈍感なのだろう。きっと大病になってから空(むな)しく過ごしてきた過去を悔い、迫り来る死に慄(おのの)きながら「ちょっと待って!」と心で叫んで死んでゆくのだろう。
ギャンブルには死を感じさせる場面がある。素寒貧(すかんぴん)になればお陀仏だ。金が払えないとなれば袋叩きにされ、金額次第では海の藻屑か山の土にされてしまう。
福本はギャンブルという舞台を通して人生の縮図を描く。
ニュートンとかガリレオは
たいくつなんてしないさ…
あいつら引力なんていう
目に見えないものまで見えて……
この大地が高速でまわっていることにさえ
気がついてしまう──(『天 天和通りの快男児』)
【『福本伸行 人生を逆転する名言集 2 迷妄と矜持の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編(竹書房、2010年)以下同】
知は退屈を退ける。生まれ立ての赤ん坊を見るがいい。彼らは退屈を知らない。清らかなタブラ・ラサには宇宙の神秘が映っているのだろう。
金を掴(つか)んでないからだ……!
金を掴んでないから毎日がリアルじゃねえんだよ
頭にカスミがかかってんだ
バスケットボールのゴールは適当な高さにあるから
みんなシュートの練習をするんだぜ
あれが100メートル先にあってみろ
誰もボールを投げようともしねえ(『賭博黙示録カイジ』)
生のリアリティは死に支えられている。つまり死を感じるところに生の味わいがあるのだ。飢えたる人の食べ物を欲するが如く、渇した人の水を求めるが如く、生を味わい尽くす人はいない。
一か八(ばち)かの勝負はヒリヒリする。コーナーを高速で攻めるスピード狂のようなものだ。それが病みつきになると依存症に陥る。
砂や石や水…
通常気 俺たちが生命などないと思ってるものも
永遠と言っていい 長い時間のサイクルの中で
変化し続けていて
それはイコール
俺たちの計(はか)りを超(こ)えた…
生命なんじゃないか…と……!
死ぬことは……
その命に戻ることだ…!(『天 天和通りの快男児』)
生という現象があり、死という現象がある。花は咲き、そして散る。人は生まれ、そして死ぬ。きっと私の人生は波のような現象なのだろう。大いなる海から生まれ、寄せては返す変化を体現しているのだ。
善悪や道徳は
無能な人間の最後のよりどころ
惑(まど)わされることはない(『銀と金』)
善悪を言葉にすると安っぽくなる。嘘の臭いまで発する。善は論じるものではなく行うべきものだ。今時は偽善が多すぎる。
闇こそ暴君(ぼうくん)…!
人間は闇の狭間(はざま)で束(つか)の間(ま)…漂(ただよ)う…
その笹舟(ささぶね)の乗員
か弱い……!
説明不能に生まれ……時が経てば死んでいく……!
それだけ……!
解答などないっ…!(『アカギ 闇に降り立った天才』)
人は安心を求めて答えを探す。挙げ句の果てに他人の言葉にしがみつく。溺れる者が藁(わら)をもつかむようにして。浮き輪を探すよりも自分の力で泳げ。力尽きれば、それもまた人生だ。
祈るようになったら人間も終わりって話だ……!(『賭博破戒録カイジ』)
エゴイストの祈りは自分の都合に合わせて行われる。坐して祈るのは現実逃避の姿だ。ぎりぎりの努力を惜しまず、限界の向こう側を目指す者だけが奇蹟を起こせる。人類はいまだに平和の祈りすらかなえていない。
この…意識が眠っているような感覚…
体を薄い膜(まく)で何層(なんそう)となく覆(おお)われ…
次第に無気力…
何をやるにも大儀(たいぎ)で面倒(めんどう)…
まるで…
薄く死んでいくような
この感覚
こんな毎日よりましかもしれない……
そう……
まだ苦しみの方が……!(『天 天和通りの快男児』)
これがギャンブラーの悟りだ。大衆消費社会を現実に動かしているのは広告会社である。政治・経済・メディアなどの情報は全て、広告効果というバイアス(歪み)が掛けられている。その刺激はサブリミナル領域(意識下)にまで働きかける。我々はベルの音を聞くとヨダレが出るようになっている。
総じて1よりも出来は悪い。私くらいの年齢になると解説も余計に感じる。それでも福本が振るう鞭は心地よい。
福本伸行 人生を逆転する名言集 2
posted with amazlet at 17.08.18
福本 伸行 橋富 政彦
竹書房
売り上げランキング: 110,582
竹書房
売り上げランキング: 110,582
ノーバート・ウィーナー、佐藤俊樹、伊藤銀月
3冊挫折。
挫折44『サイバネティックス 動物と機械における制御と通信』ノーバート・ウィーナー:池原止戈夫〈いけはら・しかお〉、彌永昌吉〈いやなが・しょうきち〉、室賀三郎、戸田巌訳(岩波文庫、2011年/岩波書店、1961年)/横書きだった。古い著作なので思い切って抄訳にしてもよかったのではあるまいか。
挫折45『〔新世紀版〕ノイマンの夢・近代の欲望 社会は情報化の夢を見る』佐藤俊樹(河出文庫、2010年/講談社選書メチエ、1996年)/文章に締まりがない。砕けた調子がかえって文章をふらつかせている。どこを読んでも総花的な印象を受ける。私が求めていた内容ではなかった。
挫折46『日本警語史』伊藤銀月〈いとう・ぎんげつ〉(講談社学術文庫、1989年)/文語体であった。緒論だけでもお釣りのくる内容。格調高い毒々しさが堪(たま)らない。これはいつか再読したい。
2011-07-19
ティク・ナット・ハン
1冊読了。
48冊目『小説ブッダ いにしえの道、白い雲』ティク・ナット・ハン:池田久代訳(春秋社、2008年)/本書は「読む瞑想」である。少なからず仏法を行ずる者であれば、宗派を問わずひもとくべき一書だ。81章の全てに小乗教の出典が明記されている。中村元〈なかむら・はじめ〉の初期仏典に先んじて読んでおきたい。日本の鎌倉仏教は時代の制約もあり歪んだブッダ像となっている。大乗仏教の精神そのものが誤っているとは思わないが政治的臭みは一掃すべきであろう。本来、仏法とは理法であって教義ではない。時代考証と合理性を踏まえながら進化し続けるのが正しい仏法のあり方だと思う。その意味で本書に生き生きと描かれたブッダの姿はストンと腑に落ちる。ティク・ナット・ハンはベトナム出身の禅僧で、「社会に関わる仏教」(エンゲイジド・ブディズム)をモットーに、コロンビア大学、ソルボンヌ大学でも教鞭を執る。翻訳も素晴らしい。
虚空と飛鳥
虚空は空虚にして飛鳥は実有なり。されど、飛鳥は空虚にして虚空は実有なりとはこれ如何。
— h a l * (@halfuziwara) July 17, 2011
虚空に水なし。されど大気と光あり。大気なければ鳥飛ぶことかなわず。有無の二道に偏することなかれ。虚空あれば鳥あり。鳥あれば虚空存する。これ縁起と申して中道実相なり。
— 小野不一 (@fuitsuono) July 18, 2011
2011-07-18
水槽の脳
ペンフィールドが1930年代に行なった古典的な脳の実験は、ある有名な謎の元になった。その後ずっと哲学の学徒からは「水槽の脳」と呼ばれている問題である。こんな話だ。「あなたはそこに座ってこの本を読んでいると思っている。実はあなたは、どこかの実験室で体から切り離され、培養液の入った水槽に入れられた脳だけの存在かもしれない。その脳に電極がつながれ、あやしげな科学者(マッド・サイエンティスト)が電気刺激を流し込み、それでまさにこの本を読んでいるという体験を引き起こしているのだ」
【『パラドックス大全』ウィリアム・ストーン:松浦俊介訳(青土社、2004年)】
・Wikipedia
・心の哲学まとめWiki
・荘子と『水槽の脳』。
クリシュナムルティの愛人スキャンダルについて
クリシュナムルティの翻訳をしてきた大野龍一が邦訳未刊の暴露本を紹介している。盟友で当初、クリシュナムルティ財団の切り盛りをしていたラージャゴパル。彼の夫人がクリシュナムルティと愛人関係にあったという内容だ。しかも20年間に及んだという。
・クリシュナムルティと二重人格
ジョン・グレイもこの本を根拠に批判していたのだろう。
・ジョン・グレイのクリシュナムルティ批判/『わらの犬 地球に君臨する人間』ジョン・グレイ
私の所感は、「フーーーン」ってところだ。もう少し詳しく述べると「そういう本が発行されているってことね」以上、である。
大野の論法でいけば、ある程度のボリュームがあって文章が上手ければ全て事実となってしまう。
ではまず基本的なことから考察しよう。浮気をしたのはラージャゴパル夫人である。その後、離婚したのかどうはわからない。ただ長期間にわたってクリシュナムルティとラージャゴパルは財団運営を巡り裁判で争っていた。
で、この本はラージャゴパル夫人の娘が執筆している。実母の浮気を世間に公開する目的は何か? 最初に想定されるのは金銭であろう。続いて報復。私としては既に道ならぬ行為をした人物が「娘にだけ真実を語った」ということは考えにくい。
大野のブログには、クリシュナムルティの翻訳を巡って様々なトラブルがあったことが書かれている。
・「クリシュナムルティ病」について(改)
クリシュナムルティの大半の翻訳を行ってきた大野純一(有限会社コスモス・ライブラリー社主)を非難している。「甚だしい見当違い」「頑固に思い込んでいる」「もっと悪質な氏の嘘を指摘しておく」「氏の鈍重・卑小な『エゴ』」「氏の杜撰な仕事ぶりには文字どおり度肝を抜かれた」「僕はその尻拭いに追われて疲労困憊した」という言葉は批判というよりも人格攻撃に近い。
・僕がクリシュナムルティの翻訳をやめたわけ(改)
こちらはクリシュナムルティ財団との悶着(もんちゃく)である。そして再び大野純一を攻撃している。翻訳の舞台裏は何のために書かれたのか? 文章から伝わってくるのは怒りだ。怒りを手放すことなく文末に至っているため、実に後味の悪い文章となっている。
・お困りネットレビュアーの精神分析
怒りの矛先はamazonのレビュワーにまで向けられる。ただ、これに関しては「エヴァンジル」なる人物が、藤仲孝司の関係者っぽい印象を受けた。藤仲本人だとしても驚くには値しない。
・『時間の終焉』を推す
リンクは時系列順で紹介している。ここでは一転して、大野純一から本を進呈されて大喜びした旨が書かれている。大野龍一はたぶん神経質な性格で傷つきやすいタイプの人間なのだろう。目まぐるしい心の振幅がそれを物語っている。
彼がスキャンダル本を鵜呑みにしたのはこうした背景と無縁ではあるまい。それとも大野は週刊誌などの記事も事実だと思い込んでいるのだろうか?
確認しようのないことを、あれこれ思いあぐねても仕方がない。ブッダにも愛人スキャンダルがあった。人を貶(おとし)める手法としては古典的なものだ。
なお基本的なことではあるが、悟りの状態はLSDを服用した場合とそっくりであることはよく知られている。更にそれは癲癇(てんかん)の発作とも酷似しており、側頭葉が激しく反応していることが脳科学の世界で明らかになっている。
結論――私は他人の下半身にはあまり興味がない。以上。
ジェノサイドとは
ジェノサイドとは、古代ギリシャ語で種を表す genos と、ラテン語に由来し殺害を意味する cide を組み合わせた造語であり、一般に「集団殺害罪」と訳されている。それは、公人であれ私人であれ、犯した個人の刑事責任が問われる国際法上の重大犯罪である。ポーランド出身のユダヤ人法学者ラファエル・レムキン(1900~1958)がナチ・ドイツの暴力支配を告発するために著した『占領下ヨーロッパにおける枢軸国支配』(1944)でこの言葉を用いたのが嚆矢となり、その後、1948年の国連総会で採択された「集団殺害罪の予防と処罰に関する条約」(ジェノサイド条約)を通して、これに法的な定義が与えられた。(石田勇治)
【『ジェノサイドと現代世界』石田勇治、武内進一編(勉誠出版、2011年)】
・前田朗(レムキンとジェノサイド条約1~7)
枢軸時代の息吹き/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
宮城谷作品は淡さとともに幕を下ろす。長い尾を引く流星のように。田文(でんぶん)こと孟嘗君(もうしょうくん)は数千年の彼方に舞い戻る。
──なにゆえ、星はまたたくのか。
空は深い感情がつみかさなってできたような黒である。その黒をやぶって光る星は、神の感情の余滴(よてき)のようにみえた。
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
歴史には民の苦しみ、悲しみ、怨嗟が堆積(たいせき)している。重畳(ちょうじょう)たる山脈のように無念が横たわっている。星は照らすことはないが方向を指し示す。
「大愚は大賢に肖(に)ております。なんの愁(うれ)えがありましょうか」
前途が見えないと嘆く田文(でんぶん)を夏候章(かこうしょう)が励ます。物を語る力が現実に新しい解釈を施す。田文に従う人々の美しい心根は言葉の花となって薫る。そこに打算はない。強靭な確信があるだけだ。
もともと笑いには人を魅了するはたらきがあり、およそ英雄と讃(たた)えられた人は、億万人にひとりといってよい笑貌(しょうぼう)をもっていたはずである。
貧弱な笑いでは人の心をつかめない。
田文の笑いには奕々(えきえき)としたものがある。その笑いのむこうに渾厚(こんこう)としたものを暗示させる笑いでもある。
笑い声の卑しい人がいる。明るく笑えない人はストレスで身体が歪んでしまっているのだろう。今時は「フフフ」と奥床しく笑う女性も少ない。バラエティ番組の笑いは人を貶(おとし)めるものが多い。笑い声も千差万別である。
「人は、在(あ)るだけのものではない。得るものだ。わしが人を得るのは、外からそうみえるだけで、じつはわしは、人が自分を得るように手助けをしているにすぎぬ」
父・田嬰(でんえい)の食客(しょっかく)や説客(せっかく)は千人を超え、田文の代になると数千人となった。海千山千のつわものたちは思わぬところで活躍する。多様性はそれだけで強みといえる。排除の力学が作動しなくなるからだ。常識から知恵は生まれない。現状を打開するのは非常識とも思える奇抜なアイディアによることが多い。
「おそらく屈原(くつげん)どのには棄ててゆく自己はありますまい。自己に盈(み)ちた自己にとって、理想はかなたにあります。そうではなく、棄ててゆく自己に理想が具現(ぐげん)するというふしぎさをおわかりにならなかったようなので、あやうさがみえたのです」
田文を支える夏候章(かこうしょう)の言葉である。詩人として知られる屈原は政治家でもあった。人の生きざまは覚悟で決まる。屈原の弱さを夏候章は鋭く見抜いた。
僕栄(ぼくえい)の声に真実のひびきがあった。
絶望的な境遇に身をおいて、はじめて自分という者がわかった声である。人はほんとうに独(ひと)りにならなければ、自分がわからぬものか。
──ここにあるのは、苦しみが産んだ美しさだ。
と、強くおもった。
洛芭(らくは)は夭(わか)いころの美貌をぬけたところにきている。ほかのことばでいえば、天与の美貌というものは、それにこだわればこだわるほど醜さを産むもので、洛芭はそういう美貌を惜(お)しげもなく棄てて、自分の美貌を独力でつくりあげた。
人を見る眼は厳しさを伴えばこそ温かみも宿るのだ。人の苦労は苦労をした者にしかわからない。生(せい)の重みを知る者は多くを語らずとも心が通い合う。何をどう見るかは視点の高さで決まる。田文は洛芭(らくは)を娶(めと)った。
寡人(かじん)にしろ孤にしろ、この世で一人、ということであり、いわば孤児にひとしい。そういう絶対のきびしさの中にいるからこそ、万民のさびしさがわかるのである。おのれを楽しませるように万民を楽しませ、おのれをなぐさめるように万民をなぐさめる。王とはそういうものである。さらに言えば、王はそのことのみに心をくだけばよく、万民の幸福が十全(じゅうぜん)でないことに悩み苦しむ存在であるともいえる。自分との苦闘において生ずるのがほんとうの理念であり、そこを経て生ずるのが信念である。
おのれをいとおしむ者はかならず自分をみがくものであり、王としてそれをおこたった懐王は、当然のことながら臣下やことがらの良否をみぬけず、屈原(くつげん)のような忠臣を逐(お)い、敵の詐謀(さぼう)にはまらざるをえない。
楚(そ)の懐王(かいおう)は謀略に躍らされた。それにしても春秋時代の政治のダイナミズムには驚かされる。各国の強弱が緊張感をはらみながら絶妙なバランスを保っている。腕と頭に自信のある者は各国を渡り歩く。交流し流動する人々が黄河のように大陸をうねる。
田文(でんぶん)は大度に侠気をふくみ、その底に仁義をすえていた人である。
果断の人ともいえるが、無謀の人ではなかった。むしろ慎重な人で、秦を攻伐する軍を催したのは、怨(うら)みと怒りにまかせたわけではなかった。
孟嘗君は戦国四君の一人となる。秦の始皇帝によって全土が統一されるのは後のことである。諸子百家(しょしひゃっか)を通して枢軸時代の息吹きが伝わってくる。人間とはかくも巨大であったのだ。
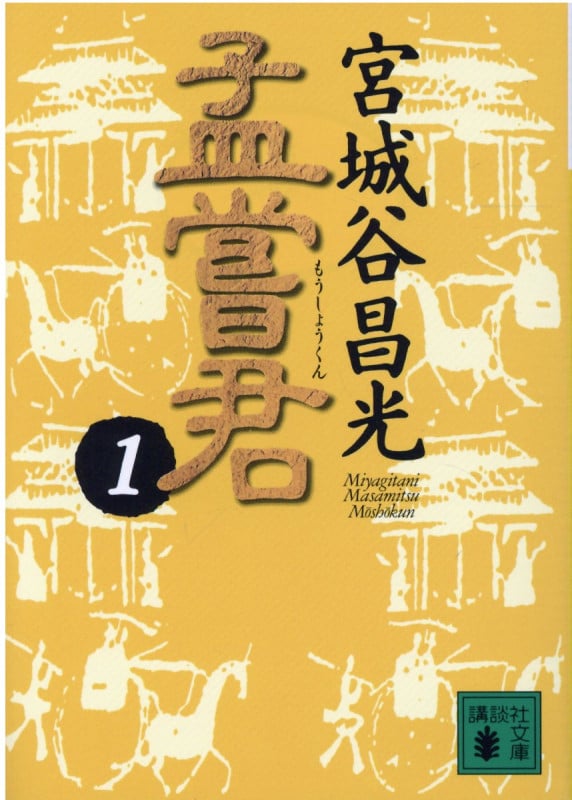




・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
2011-07-17
進化論に驚いたクリスチャン
・太陽系の本当の大きさ
・相対性理論によれば飛行機に乗ると若返る
・枕には4万匹のダニがいる
・あなた個人を終点とする長い長い系図
・陽子
・ビッグバン宇宙論
・進化論に驚いたクリスチャン
・『人類が生まれるための12の偶然』眞淳平:松井孝典監修
・『黒体と量子猫』ジェニファー・ウーレット
・『重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る』大栗博司
・『広い宇宙に地球人しか見当たらない50の理由 フェルミのパラドックス』スティーヴン・ウェッブ
・『ブラックホール戦争 スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い』レオナルド・サスキンド
・『人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか』ビル・ブライソン
先祖が猿だなんて!
本当であってほしくない。
でも本当だとしたら、
そんな話が世間に広まらないようお祈りしなくては。
――ウースター主教夫人がダーウィンの進化論を聞いたときに発したとされる言葉
【『人類が知っていることすべての短い歴史』ビル・ブライソン:楡井浩一〈にれい・こういち〉訳(NHK出版、2006年/新潮文庫、2014年)】
2011-07-16
津田真一、モーリス・オコンネル・ウォルシュ、マーシャル・マクルーハン、石田勇治、武内進一
4冊挫折。
挫折40『反密教学』津田真一(春秋社、2008年改訂新版/リブロポート、1987年)/ノリがボードリヤールと似ている。頭がいい人だ。よすぎてついてゆけず。でもまあ良心的な価格(3360円)なんで、冒頭の章の対談だけでも一読の価値あり。上級者向け。
挫折41『仏教のまなざし 仏教から見た生死の問題』モーリス・オコンネル・ウォルシュ:大野龍一訳(コスモス・ライブラリー、2008年)/スピリチュアリズムから仏教にアプローチしたような内容。「アストラル体」が出てきたところでやめる(笑)。クリシュナムルティの「輪廻転生について」が付録となっているが、読まなくても構わない代物だ。
挫折42『メディア論 人間の拡張の諸相』マーシャル・マクルーハン:栗原裕〈くりはら・ゆたか〉、河本仲聖〈こうもと・なかきよ〉訳(みすず書房、1987年)/最初は面白かったのだが、途中から胡散臭さを感じて中止。ヌルヌルしていて、つかみどころがない。たぶん意図的にやっているんだろうけどね。これは再読することもないと思う。
挫折43『ジェノサイドと現代世界』石田勇治、武内進一編(勉誠出版、2011年)/呑気かつ悠長。イライラが募ってやめる。客観性は大切であろうが、あまりの熱意のなさに驚かされる。十数人の論文で構成されているが、一つとして読む気が起こらなかった。
身体の内側から湧き起こる力
演技とは、からだ全体が躍動することであり、意識が命令するのではなく、からだがおのずから発動し、みずからを超えて行動すること。またことばとは、意識がのどに命じて発せしめる音のことではなく、からだが、むしろことばがみずから語り出すのだ。
【『ことばが劈(ひら)かれるとき』竹内敏晴(思想の科学社、1975年/ちくま文庫、1988年)】
・噴火する言葉/『大野一雄 稽古の言葉』大野一雄著、大野一雄舞踏研究所編
この国を任せたい有名人:アクサ生命アンケート調査
フランスの大手保険会社アクサ生命が1万人に行ったアンケート結果がこれ。いくつかの驚くべき事実が浮かび上がってくる。
まず国会議員が小沢一郎ただ一人しかいない。アンケートの母数に年齢・地域・職業・性別などで偏りがなければ、1万という数は全国の平均を示していると考えてよかろう(アクサ生命のサイトに情報が上がっていないため何とも言い難いのだが)。
そしてテレビを全く視聴しない私としては東国原英夫〈ひがしこくばる・ひでお〉に注目せざるを得ない。昔から色んな噂が耐えない人物だ。ひょっとしてあれか、宮崎県の知事選挙で「どげんかせんといかん」と連呼した声が、いまだに脳内で反響している人々が多いってことなのか? あるいは宮崎の営業マンとしての平身低頭ぶりを好ましく思っている人が多いのだろうか? 全く理解に苦しむ。
手っ取り早く結論を述べよう。このアンケートはメガトン級の破壊力を持っている。なぜかといえば、外国人が二人も入っているからだ。
少し精査してみよう。北海道大学医学部の名誉教授が次のように語ったことがある。「統計学的に見れば10人に1人はおかしな人間と想定される」と。では早速計算してみよう。
・1万人のうち1000人はおかしい=9000人
・カルロス・ゴーン+バラク・オバマ=288
・母数に対する割合=288÷9000=3.2%
・10位内に対する割合=288÷2711=10.6%
ってことはだよ、日本人全体のうち、10.6%もの国民が外国人に自国を任せようとしていることになる。
容易に想像できることではあるが、その中には当然次のようなアンケート回答があったはずだ。
・キム・ジョンイル(ネタです)
・やっぱ、カダフィでしょー。
・(任せることのできる=偉人、という脳内条件反射によって)ナポレオン
・(ジョン・F・ケネディが頭に浮かび、自動的に導かれたのが)ケビン・コスナー
・(任せる=最強、ってことで)プーチン
・(ただ何となく)アウンサン・スーチー
おわかりだろうか。国家が独立している意味すら知らない国民が1割も存在するのだ。つまり、この国の10%は国家の態(てい)を成していないことになる。
今尚続く戦後の枠組みの中で、日本はアメリカの属国に甘んじている。やくざ者に強姦され、その後情婦になったような関係性を我が国は維持している。米国の現大統領に自国を任せたいというのは、強姦したやくざ者を戸籍上の父親にするようなものだろう。
日本の1割は完全に崩壊しているといってよい。
サブラ・シャティーラ事件
サブア大通りで、瓦礫とともにぐしゃぐしゃに砕けた男の死体が二つあった。その先に杖のころがったわきで、手を胸のところに固く握りしめる老人が一人、その近くのもう一人の老人の体の下からは、安全ピンを抜いた手榴弾が見えた。この死体にふれると爆発する仕掛けになっていると理解するまで、かなりの時間がかかった。道いっぱいに脳漿が吹き飛んで、そこにハエが群がる中で、私はぼうぜんと立ち尽くした。
一人が、路地にうつぶせに倒れていた。男か女か分からないが、ハンカチを頭の上にかぶせてある。のちの証言によると、この人は頭をオノで割られたのだという。男たちが折り重なって倒れていたのは少し丘に上った土の壁の前で、そこには無数の弾痕が見えた。そして一軒の家の庭には、その家の住民と思われる女と子どもたちが、やはり瓦礫の上に投げ出されていた。一番上に幼児が、うつぶせになっているのは、おそらく叩きつけられたのだろう。さるぐつわをかまされた女性が、服をひきさかれて死んでいた。チェックのスカートの女の子が、手を差し伸べるようにして殺され、その隣りに歩いているような姿勢で殺された男の子は、首を針金のようなもので縛られていた。別のガレージには、縛られてトラックにひきずられてきた人々が殺されていた。背の低い小柄な老人が、胸の上に鍵を置いて死んでいた。パレスチナ人たちは、いつか故郷に戻る日のために、かつての自分の家の鍵をいつも持ち歩いている、という話を私は思い起こした。
【『パレスチナ 新版』広河隆一〈ひろかわ・りゅういち〉(岩波新書、2002年)】
・「ベイルート虐殺事件から20年」広河隆一
・パレスチナの歴史:サブラ・シャティーラの虐殺
田文の光彩に満ちた春秋/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
物語は第4巻でクライマックスに至る。敢えてそう書いておこう。宮城谷作品は、ある種の透明感をもって幕を下ろすのが特徴だ。人が歴史に溶け込むような印象を受ける。目の前で躍るように活躍していた登場人物が、再び歴史の彼方へと去ってゆくのだ。
田忌(でんき)と鄒忌(すうき)の政争、白圭(はくけい)の堤防事業、田文(でんぶん)と洛芭(らくは)の運命的な出会い。歴史の歯車が音を立てて回り始める。
「田忌(でんき)将軍のご気性からすると、善を喜び、悪を憎むことがどちらもはげしい。それをけむたがる者は、善の仮面をつけて悪をおこなう」
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
宋江(そうこう)が『水滸伝』の主役となっている意味が初めて腑に落ちた。清らかな権力者は必ず他人にも厳しくなる。当然、恨みを買う場面も増える。気づかぬうちに不満分子が寄り集まる。そこに鄒忌(すうき)が付け込む隙(すき)があったといえる。
斉(せい)の貴族のなかで、いや、中国の貴族のなかで、食客(しょっかく)をかかえはじめたのは、田嬰(でんえい)が最初であろう。
孫ピンの下(もと)で学んだ田文が今度は食客に揉まれながら著しい成長を遂げる。食客は臣下ではない。このため恩を感じても、忠を尽くす義務はない。主人を助ける助けないも彼らの自発による。若き田文は食客たちの心をつかんでゆく。後々彼らは田文を大いに助けることとなる。
――人には他人にいえぬことがある。
それをことばではなく、心でわかることが、ほんとうにわかるということではないのか。真意というものはことばにすると妄(うそ)になる。だから、いわない。黙っていることが真実なのである。
これを私は27歳の時に知った。人生を変えるほどの感動に包まれたことがあった。それを友人たちの前で語ろうとしてやめた。「言葉にすると嘘になるから」と私は言った。もちろん文脈は異なっているが、言葉にできぬ思いという点では一致している。
また、30代半ばではこんなこともあった。後輩の父親が二度にわたって自殺未遂をして行方不明となった。半年後に首を吊った遺体が発見された。風の如く後輩の家を訪ねると、いつもと変わらぬ姿があった。お母さんと妹もニコニコしていた。座卓を囲みしばし沈黙した後、私は後輩の膝を思い切り叩き、「すまん、何もできなかったよ!」と言うなり泣いた。その瞬間、居合わせた全員がわっと声を上げて泣いた。ただ泣いた。泣いて泣いて泣き抜いた。言葉は要らなかった。
長い人生にはそういうことが何度かあるものだ。真の理解は沈黙の底から生まれる。
「文(ぶん)どのはよい声をしておられる。じつにすがすがしい。天と地とが和したような声だ。億万人にひとりの声だ、と申しておこう」
声の響きが大切である。声はその人の生命の反響である。文章は嘘をつけるが、声は誤魔化せない。
――外交は目でするものではない。耳でするものだ。
それが田嬰(でんえい)のかけひきの秘訣(ひけつ)であった。
父・田嬰(でんえい)も声から相手を見抜くことができる人物であった。聞く人が聞けば、おのずと正邪のバイブレーションがわかるものだ。
白圭(はくけい)は私財をなげうって黄河の堤防事業を開始する。商いで稼いだ金を民に返すというのが持論であった。白圭と再会した田文(でんぶん)は右腕として事業の指揮をとる。そこで赤子(あかご)の時、一緒にさらわれた洛芭(らくは)と巡り会う。
田文(でんぶん)は光彩に満ちた春秋を歩む。彼には焦りがない。そして、じっくりと時を待つ肚(はら)ができていた。
数千年の時を超えて英雄が立ち上がってくる。足腰の力がなければ踏みこたえることができない。前屈(かが)みの姿勢で本書を開くべきだ。
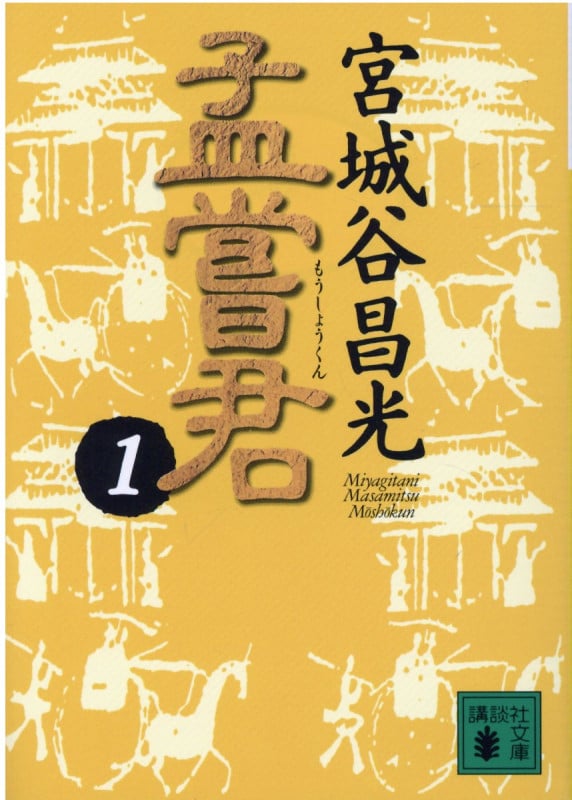




・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
登録:
コメント (Atom)











