2011-07-21
人間は人間にとって鏡なのである
人間は人間にとって鏡なのである。鏡というものは、物を光景(スペクタル)に、光景を物に変え、私を他人に、他人を私に変える万能魔術の道具なのだ。これまでもしばしば、画家たちは鏡について思いを凝らしてきた。それというのも、彼らは遠近法というトリックのばあいと同様に、鏡というこの「機械的トリック」のもとでも、〈見る者〉と〈見えるもの〉との転換を認めたからであり、そしてこの転換こそ、ほかならぬわれわれの肉体の定義であり、また画家の使命の定義なのである。
【『眼と精神』M・メルロ=ポンティ:滝浦静雄、木田元〈きだ・げん〉訳(みすず書房、1966年)】
2011-07-20
ギャンブラーの哲学/『福本伸行 人生を逆転する名言集 2 迷妄と矜持の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編
・『銀と金』福本伸行
・『賭博黙示録カイジ』福本伸行
・『福本伸行 人生を逆転する名言集 覚醒と不屈の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編
・ギャンブラーの哲学
・『無境界の人』森巣博
・『賭けるゆえに我あり』森巣博
・『真剣師 小池重明 “新宿の殺し屋"と呼ばれた将棋ギャンブラーの生涯』団鬼六
金を賭けるのがギャンブルなら、時間を賭けるのが人生といえるだろう。
「諸君は永久に生きられるかのように生きている」とセネカが糾弾している。生と死の理(ことわり)を思索することもなく、肝心なことは全部先送りにしながら我々は年老いてゆく。
今この瞬間も刻一刻と死が迫っているのに平然と構えているのはどうしたことか。なぜこれほど鈍感なのだろう。きっと大病になってから空(むな)しく過ごしてきた過去を悔い、迫り来る死に慄(おのの)きながら「ちょっと待って!」と心で叫んで死んでゆくのだろう。
ギャンブルには死を感じさせる場面がある。素寒貧(すかんぴん)になればお陀仏だ。金が払えないとなれば袋叩きにされ、金額次第では海の藻屑か山の土にされてしまう。
福本はギャンブルという舞台を通して人生の縮図を描く。
ニュートンとかガリレオは
たいくつなんてしないさ…
あいつら引力なんていう
目に見えないものまで見えて……
この大地が高速でまわっていることにさえ
気がついてしまう──(『天 天和通りの快男児』)
【『福本伸行 人生を逆転する名言集 2 迷妄と矜持の言葉たち』福本伸行著、橋富政彦編(竹書房、2010年)以下同】
知は退屈を退ける。生まれ立ての赤ん坊を見るがいい。彼らは退屈を知らない。清らかなタブラ・ラサには宇宙の神秘が映っているのだろう。
金を掴(つか)んでないからだ……!
金を掴んでないから毎日がリアルじゃねえんだよ
頭にカスミがかかってんだ
バスケットボールのゴールは適当な高さにあるから
みんなシュートの練習をするんだぜ
あれが100メートル先にあってみろ
誰もボールを投げようともしねえ(『賭博黙示録カイジ』)
生のリアリティは死に支えられている。つまり死を感じるところに生の味わいがあるのだ。飢えたる人の食べ物を欲するが如く、渇した人の水を求めるが如く、生を味わい尽くす人はいない。
一か八(ばち)かの勝負はヒリヒリする。コーナーを高速で攻めるスピード狂のようなものだ。それが病みつきになると依存症に陥る。
砂や石や水…
通常気 俺たちが生命などないと思ってるものも
永遠と言っていい 長い時間のサイクルの中で
変化し続けていて
それはイコール
俺たちの計(はか)りを超(こ)えた…
生命なんじゃないか…と……!
死ぬことは……
その命に戻ることだ…!(『天 天和通りの快男児』)
生という現象があり、死という現象がある。花は咲き、そして散る。人は生まれ、そして死ぬ。きっと私の人生は波のような現象なのだろう。大いなる海から生まれ、寄せては返す変化を体現しているのだ。
善悪や道徳は
無能な人間の最後のよりどころ
惑(まど)わされることはない(『銀と金』)
善悪を言葉にすると安っぽくなる。嘘の臭いまで発する。善は論じるものではなく行うべきものだ。今時は偽善が多すぎる。
闇こそ暴君(ぼうくん)…!
人間は闇の狭間(はざま)で束(つか)の間(ま)…漂(ただよ)う…
その笹舟(ささぶね)の乗員
か弱い……!
説明不能に生まれ……時が経てば死んでいく……!
それだけ……!
解答などないっ…!(『アカギ 闇に降り立った天才』)
人は安心を求めて答えを探す。挙げ句の果てに他人の言葉にしがみつく。溺れる者が藁(わら)をもつかむようにして。浮き輪を探すよりも自分の力で泳げ。力尽きれば、それもまた人生だ。
祈るようになったら人間も終わりって話だ……!(『賭博破戒録カイジ』)
エゴイストの祈りは自分の都合に合わせて行われる。坐して祈るのは現実逃避の姿だ。ぎりぎりの努力を惜しまず、限界の向こう側を目指す者だけが奇蹟を起こせる。人類はいまだに平和の祈りすらかなえていない。
この…意識が眠っているような感覚…
体を薄い膜(まく)で何層(なんそう)となく覆(おお)われ…
次第に無気力…
何をやるにも大儀(たいぎ)で面倒(めんどう)…
まるで…
薄く死んでいくような
この感覚
こんな毎日よりましかもしれない……
そう……
まだ苦しみの方が……!(『天 天和通りの快男児』)
これがギャンブラーの悟りだ。大衆消費社会を現実に動かしているのは広告会社である。政治・経済・メディアなどの情報は全て、広告効果というバイアス(歪み)が掛けられている。その刺激はサブリミナル領域(意識下)にまで働きかける。我々はベルの音を聞くとヨダレが出るようになっている。
総じて1よりも出来は悪い。私くらいの年齢になると解説も余計に感じる。それでも福本が振るう鞭は心地よい。
竹書房
売り上げランキング: 110,582
ノーバート・ウィーナー、佐藤俊樹、伊藤銀月
3冊挫折。
挫折44『サイバネティックス 動物と機械における制御と通信』ノーバート・ウィーナー:池原止戈夫〈いけはら・しかお〉、彌永昌吉〈いやなが・しょうきち〉、室賀三郎、戸田巌訳(岩波文庫、2011年/岩波書店、1961年)/横書きだった。古い著作なので思い切って抄訳にしてもよかったのではあるまいか。
挫折45『〔新世紀版〕ノイマンの夢・近代の欲望 社会は情報化の夢を見る』佐藤俊樹(河出文庫、2010年/講談社選書メチエ、1996年)/文章に締まりがない。砕けた調子がかえって文章をふらつかせている。どこを読んでも総花的な印象を受ける。私が求めていた内容ではなかった。
挫折46『日本警語史』伊藤銀月〈いとう・ぎんげつ〉(講談社学術文庫、1989年)/文語体であった。緒論だけでもお釣りのくる内容。格調高い毒々しさが堪(たま)らない。これはいつか再読したい。
2011-07-19
ティク・ナット・ハン
1冊読了。
48冊目『小説ブッダ いにしえの道、白い雲』ティク・ナット・ハン:池田久代訳(春秋社、2008年)/本書は「読む瞑想」である。少なからず仏法を行ずる者であれば、宗派を問わずひもとくべき一書だ。81章の全てに小乗教の出典が明記されている。中村元〈なかむら・はじめ〉の初期仏典に先んじて読んでおきたい。日本の鎌倉仏教は時代の制約もあり歪んだブッダ像となっている。大乗仏教の精神そのものが誤っているとは思わないが政治的臭みは一掃すべきであろう。本来、仏法とは理法であって教義ではない。時代考証と合理性を踏まえながら進化し続けるのが正しい仏法のあり方だと思う。その意味で本書に生き生きと描かれたブッダの姿はストンと腑に落ちる。ティク・ナット・ハンはベトナム出身の禅僧で、「社会に関わる仏教」(エンゲイジド・ブディズム)をモットーに、コロンビア大学、ソルボンヌ大学でも教鞭を執る。翻訳も素晴らしい。
虚空と飛鳥
虚空は空虚にして飛鳥は実有なり。されど、飛鳥は空虚にして虚空は実有なりとはこれ如何。
— h a l * (@halfuziwara) July 17, 2011
虚空に水なし。されど大気と光あり。大気なければ鳥飛ぶことかなわず。有無の二道に偏することなかれ。虚空あれば鳥あり。鳥あれば虚空存する。これ縁起と申して中道実相なり。
— 小野不一 (@fuitsuono) July 18, 2011
2011-07-18
水槽の脳
ペンフィールドが1930年代に行なった古典的な脳の実験は、ある有名な謎の元になった。その後ずっと哲学の学徒からは「水槽の脳」と呼ばれている問題である。こんな話だ。「あなたはそこに座ってこの本を読んでいると思っている。実はあなたは、どこかの実験室で体から切り離され、培養液の入った水槽に入れられた脳だけの存在かもしれない。その脳に電極がつながれ、あやしげな科学者(マッド・サイエンティスト)が電気刺激を流し込み、それでまさにこの本を読んでいるという体験を引き起こしているのだ」
【『パラドックス大全』ウィリアム・ストーン:松浦俊介訳(青土社、2004年)】
・Wikipedia
・心の哲学まとめWiki
・荘子と『水槽の脳』。
クリシュナムルティの愛人スキャンダルについて
クリシュナムルティの翻訳をしてきた大野龍一が邦訳未刊の暴露本を紹介している。盟友で当初、クリシュナムルティ財団の切り盛りをしていたラージャゴパル。彼の夫人がクリシュナムルティと愛人関係にあったという内容だ。しかも20年間に及んだという。
・クリシュナムルティと二重人格
ジョン・グレイもこの本を根拠に批判していたのだろう。
・ジョン・グレイのクリシュナムルティ批判/『わらの犬 地球に君臨する人間』ジョン・グレイ
私の所感は、「フーーーン」ってところだ。もう少し詳しく述べると「そういう本が発行されているってことね」以上、である。
大野の論法でいけば、ある程度のボリュームがあって文章が上手ければ全て事実となってしまう。
ではまず基本的なことから考察しよう。浮気をしたのはラージャゴパル夫人である。その後、離婚したのかどうはわからない。ただ長期間にわたってクリシュナムルティとラージャゴパルは財団運営を巡り裁判で争っていた。
で、この本はラージャゴパル夫人の娘が執筆している。実母の浮気を世間に公開する目的は何か? 最初に想定されるのは金銭であろう。続いて報復。私としては既に道ならぬ行為をした人物が「娘にだけ真実を語った」ということは考えにくい。
大野のブログには、クリシュナムルティの翻訳を巡って様々なトラブルがあったことが書かれている。
・「クリシュナムルティ病」について(改)
クリシュナムルティの大半の翻訳を行ってきた大野純一(有限会社コスモス・ライブラリー社主)を非難している。「甚だしい見当違い」「頑固に思い込んでいる」「もっと悪質な氏の嘘を指摘しておく」「氏の鈍重・卑小な『エゴ』」「氏の杜撰な仕事ぶりには文字どおり度肝を抜かれた」「僕はその尻拭いに追われて疲労困憊した」という言葉は批判というよりも人格攻撃に近い。
・僕がクリシュナムルティの翻訳をやめたわけ(改)
こちらはクリシュナムルティ財団との悶着(もんちゃく)である。そして再び大野純一を攻撃している。翻訳の舞台裏は何のために書かれたのか? 文章から伝わってくるのは怒りだ。怒りを手放すことなく文末に至っているため、実に後味の悪い文章となっている。
・お困りネットレビュアーの精神分析
怒りの矛先はamazonのレビュワーにまで向けられる。ただ、これに関しては「エヴァンジル」なる人物が、藤仲孝司の関係者っぽい印象を受けた。藤仲本人だとしても驚くには値しない。
・『時間の終焉』を推す
リンクは時系列順で紹介している。ここでは一転して、大野純一から本を進呈されて大喜びした旨が書かれている。大野龍一はたぶん神経質な性格で傷つきやすいタイプの人間なのだろう。目まぐるしい心の振幅がそれを物語っている。
彼がスキャンダル本を鵜呑みにしたのはこうした背景と無縁ではあるまい。それとも大野は週刊誌などの記事も事実だと思い込んでいるのだろうか?
確認しようのないことを、あれこれ思いあぐねても仕方がない。ブッダにも愛人スキャンダルがあった。人を貶(おとし)める手法としては古典的なものだ。
なお基本的なことではあるが、悟りの状態はLSDを服用した場合とそっくりであることはよく知られている。更にそれは癲癇(てんかん)の発作とも酷似しており、側頭葉が激しく反応していることが脳科学の世界で明らかになっている。
結論――私は他人の下半身にはあまり興味がない。以上。
ジェノサイドとは
ジェノサイドとは、古代ギリシャ語で種を表す genos と、ラテン語に由来し殺害を意味する cide を組み合わせた造語であり、一般に「集団殺害罪」と訳されている。それは、公人であれ私人であれ、犯した個人の刑事責任が問われる国際法上の重大犯罪である。ポーランド出身のユダヤ人法学者ラファエル・レムキン(1900~1958)がナチ・ドイツの暴力支配を告発するために著した『占領下ヨーロッパにおける枢軸国支配』(1944)でこの言葉を用いたのが嚆矢となり、その後、1948年の国連総会で採択された「集団殺害罪の予防と処罰に関する条約」(ジェノサイド条約)を通して、これに法的な定義が与えられた。(石田勇治)
【『ジェノサイドと現代世界』石田勇治、武内進一編(勉誠出版、2011年)】
・前田朗(レムキンとジェノサイド条約1~7)
枢軸時代の息吹き/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
宮城谷作品は淡さとともに幕を下ろす。長い尾を引く流星のように。田文(でんぶん)こと孟嘗君(もうしょうくん)は数千年の彼方に舞い戻る。
──なにゆえ、星はまたたくのか。
空は深い感情がつみかさなってできたような黒である。その黒をやぶって光る星は、神の感情の余滴(よてき)のようにみえた。
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
歴史には民の苦しみ、悲しみ、怨嗟が堆積(たいせき)している。重畳(ちょうじょう)たる山脈のように無念が横たわっている。星は照らすことはないが方向を指し示す。
「大愚は大賢に肖(に)ております。なんの愁(うれ)えがありましょうか」
前途が見えないと嘆く田文(でんぶん)を夏候章(かこうしょう)が励ます。物を語る力が現実に新しい解釈を施す。田文に従う人々の美しい心根は言葉の花となって薫る。そこに打算はない。強靭な確信があるだけだ。
もともと笑いには人を魅了するはたらきがあり、およそ英雄と讃(たた)えられた人は、億万人にひとりといってよい笑貌(しょうぼう)をもっていたはずである。
貧弱な笑いでは人の心をつかめない。
田文の笑いには奕々(えきえき)としたものがある。その笑いのむこうに渾厚(こんこう)としたものを暗示させる笑いでもある。
笑い声の卑しい人がいる。明るく笑えない人はストレスで身体が歪んでしまっているのだろう。今時は「フフフ」と奥床しく笑う女性も少ない。バラエティ番組の笑いは人を貶(おとし)めるものが多い。笑い声も千差万別である。
「人は、在(あ)るだけのものではない。得るものだ。わしが人を得るのは、外からそうみえるだけで、じつはわしは、人が自分を得るように手助けをしているにすぎぬ」
父・田嬰(でんえい)の食客(しょっかく)や説客(せっかく)は千人を超え、田文の代になると数千人となった。海千山千のつわものたちは思わぬところで活躍する。多様性はそれだけで強みといえる。排除の力学が作動しなくなるからだ。常識から知恵は生まれない。現状を打開するのは非常識とも思える奇抜なアイディアによることが多い。
「おそらく屈原(くつげん)どのには棄ててゆく自己はありますまい。自己に盈(み)ちた自己にとって、理想はかなたにあります。そうではなく、棄ててゆく自己に理想が具現(ぐげん)するというふしぎさをおわかりにならなかったようなので、あやうさがみえたのです」
田文を支える夏候章(かこうしょう)の言葉である。詩人として知られる屈原は政治家でもあった。人の生きざまは覚悟で決まる。屈原の弱さを夏候章は鋭く見抜いた。
僕栄(ぼくえい)の声に真実のひびきがあった。
絶望的な境遇に身をおいて、はじめて自分という者がわかった声である。人はほんとうに独(ひと)りにならなければ、自分がわからぬものか。
──ここにあるのは、苦しみが産んだ美しさだ。
と、強くおもった。
洛芭(らくは)は夭(わか)いころの美貌をぬけたところにきている。ほかのことばでいえば、天与の美貌というものは、それにこだわればこだわるほど醜さを産むもので、洛芭はそういう美貌を惜(お)しげもなく棄てて、自分の美貌を独力でつくりあげた。
人を見る眼は厳しさを伴えばこそ温かみも宿るのだ。人の苦労は苦労をした者にしかわからない。生(せい)の重みを知る者は多くを語らずとも心が通い合う。何をどう見るかは視点の高さで決まる。田文は洛芭(らくは)を娶(めと)った。
寡人(かじん)にしろ孤にしろ、この世で一人、ということであり、いわば孤児にひとしい。そういう絶対のきびしさの中にいるからこそ、万民のさびしさがわかるのである。おのれを楽しませるように万民を楽しませ、おのれをなぐさめるように万民をなぐさめる。王とはそういうものである。さらに言えば、王はそのことのみに心をくだけばよく、万民の幸福が十全(じゅうぜん)でないことに悩み苦しむ存在であるともいえる。自分との苦闘において生ずるのがほんとうの理念であり、そこを経て生ずるのが信念である。
おのれをいとおしむ者はかならず自分をみがくものであり、王としてそれをおこたった懐王は、当然のことながら臣下やことがらの良否をみぬけず、屈原(くつげん)のような忠臣を逐(お)い、敵の詐謀(さぼう)にはまらざるをえない。
楚(そ)の懐王(かいおう)は謀略に躍らされた。それにしても春秋時代の政治のダイナミズムには驚かされる。各国の強弱が緊張感をはらみながら絶妙なバランスを保っている。腕と頭に自信のある者は各国を渡り歩く。交流し流動する人々が黄河のように大陸をうねる。
田文(でんぶん)は大度に侠気をふくみ、その底に仁義をすえていた人である。
果断の人ともいえるが、無謀の人ではなかった。むしろ慎重な人で、秦を攻伐する軍を催したのは、怨(うら)みと怒りにまかせたわけではなかった。
孟嘗君は戦国四君の一人となる。秦の始皇帝によって全土が統一されるのは後のことである。諸子百家(しょしひゃっか)を通して枢軸時代の息吹きが伝わってくる。人間とはかくも巨大であったのだ。
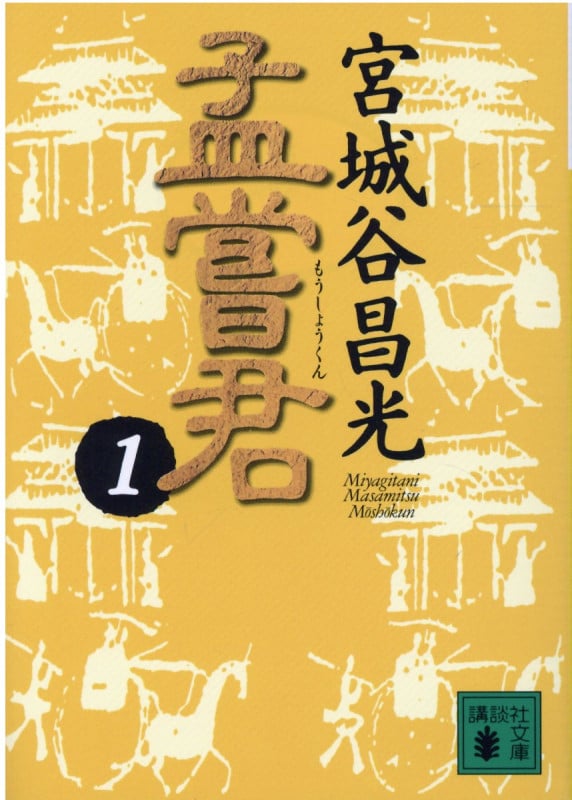




・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
2011-07-17
進化論に驚いたクリスチャン
・太陽系の本当の大きさ
・相対性理論によれば飛行機に乗ると若返る
・枕には4万匹のダニがいる
・あなた個人を終点とする長い長い系図
・陽子
・ビッグバン宇宙論
・進化論に驚いたクリスチャン
・『人類が生まれるための12の偶然』眞淳平:松井孝典監修
・『黒体と量子猫』ジェニファー・ウーレット
・『重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る』大栗博司
・『広い宇宙に地球人しか見当たらない50の理由 フェルミのパラドックス』スティーヴン・ウェッブ
・『ブラックホール戦争 スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い』レオナルド・サスキンド
・『人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか』ビル・ブライソン
先祖が猿だなんて!
本当であってほしくない。
でも本当だとしたら、
そんな話が世間に広まらないようお祈りしなくては。
――ウースター主教夫人がダーウィンの進化論を聞いたときに発したとされる言葉
【『人類が知っていることすべての短い歴史』ビル・ブライソン:楡井浩一〈にれい・こういち〉訳(NHK出版、2006年/新潮文庫、2014年)】
2011-07-16
津田真一、モーリス・オコンネル・ウォルシュ、マーシャル・マクルーハン、石田勇治、武内進一
4冊挫折。
挫折40『反密教学』津田真一(春秋社、2008年改訂新版/リブロポート、1987年)/ノリがボードリヤールと似ている。頭がいい人だ。よすぎてついてゆけず。でもまあ良心的な価格(3360円)なんで、冒頭の章の対談だけでも一読の価値あり。上級者向け。
挫折41『仏教のまなざし 仏教から見た生死の問題』モーリス・オコンネル・ウォルシュ:大野龍一訳(コスモス・ライブラリー、2008年)/スピリチュアリズムから仏教にアプローチしたような内容。「アストラル体」が出てきたところでやめる(笑)。クリシュナムルティの「輪廻転生について」が付録となっているが、読まなくても構わない代物だ。
挫折42『メディア論 人間の拡張の諸相』マーシャル・マクルーハン:栗原裕〈くりはら・ゆたか〉、河本仲聖〈こうもと・なかきよ〉訳(みすず書房、1987年)/最初は面白かったのだが、途中から胡散臭さを感じて中止。ヌルヌルしていて、つかみどころがない。たぶん意図的にやっているんだろうけどね。これは再読することもないと思う。
挫折43『ジェノサイドと現代世界』石田勇治、武内進一編(勉誠出版、2011年)/呑気かつ悠長。イライラが募ってやめる。客観性は大切であろうが、あまりの熱意のなさに驚かされる。十数人の論文で構成されているが、一つとして読む気が起こらなかった。
身体の内側から湧き起こる力
演技とは、からだ全体が躍動することであり、意識が命令するのではなく、からだがおのずから発動し、みずからを超えて行動すること。またことばとは、意識がのどに命じて発せしめる音のことではなく、からだが、むしろことばがみずから語り出すのだ。
【『ことばが劈(ひら)かれるとき』竹内敏晴(思想の科学社、1975年/ちくま文庫、1988年)】
・噴火する言葉/『大野一雄 稽古の言葉』大野一雄著、大野一雄舞踏研究所編
この国を任せたい有名人:アクサ生命アンケート調査
フランスの大手保険会社アクサ生命が1万人に行ったアンケート結果がこれ。いくつかの驚くべき事実が浮かび上がってくる。
まず国会議員が小沢一郎ただ一人しかいない。アンケートの母数に年齢・地域・職業・性別などで偏りがなければ、1万という数は全国の平均を示していると考えてよかろう(アクサ生命のサイトに情報が上がっていないため何とも言い難いのだが)。
そしてテレビを全く視聴しない私としては東国原英夫〈ひがしこくばる・ひでお〉に注目せざるを得ない。昔から色んな噂が耐えない人物だ。ひょっとしてあれか、宮崎県の知事選挙で「どげんかせんといかん」と連呼した声が、いまだに脳内で反響している人々が多いってことなのか? あるいは宮崎の営業マンとしての平身低頭ぶりを好ましく思っている人が多いのだろうか? 全く理解に苦しむ。
手っ取り早く結論を述べよう。このアンケートはメガトン級の破壊力を持っている。なぜかといえば、外国人が二人も入っているからだ。
少し精査してみよう。北海道大学医学部の名誉教授が次のように語ったことがある。「統計学的に見れば10人に1人はおかしな人間と想定される」と。では早速計算してみよう。
・1万人のうち1000人はおかしい=9000人
・カルロス・ゴーン+バラク・オバマ=288
・母数に対する割合=288÷9000=3.2%
・10位内に対する割合=288÷2711=10.6%
ってことはだよ、日本人全体のうち、10.6%もの国民が外国人に自国を任せようとしていることになる。
容易に想像できることではあるが、その中には当然次のようなアンケート回答があったはずだ。
・キム・ジョンイル(ネタです)
・やっぱ、カダフィでしょー。
・(任せることのできる=偉人、という脳内条件反射によって)ナポレオン
・(ジョン・F・ケネディが頭に浮かび、自動的に導かれたのが)ケビン・コスナー
・(任せる=最強、ってことで)プーチン
・(ただ何となく)アウンサン・スーチー
おわかりだろうか。国家が独立している意味すら知らない国民が1割も存在するのだ。つまり、この国の10%は国家の態(てい)を成していないことになる。
今尚続く戦後の枠組みの中で、日本はアメリカの属国に甘んじている。やくざ者に強姦され、その後情婦になったような関係性を我が国は維持している。米国の現大統領に自国を任せたいというのは、強姦したやくざ者を戸籍上の父親にするようなものだろう。
日本の1割は完全に崩壊しているといってよい。
サブラ・シャティーラ事件
サブア大通りで、瓦礫とともにぐしゃぐしゃに砕けた男の死体が二つあった。その先に杖のころがったわきで、手を胸のところに固く握りしめる老人が一人、その近くのもう一人の老人の体の下からは、安全ピンを抜いた手榴弾が見えた。この死体にふれると爆発する仕掛けになっていると理解するまで、かなりの時間がかかった。道いっぱいに脳漿が吹き飛んで、そこにハエが群がる中で、私はぼうぜんと立ち尽くした。
一人が、路地にうつぶせに倒れていた。男か女か分からないが、ハンカチを頭の上にかぶせてある。のちの証言によると、この人は頭をオノで割られたのだという。男たちが折り重なって倒れていたのは少し丘に上った土の壁の前で、そこには無数の弾痕が見えた。そして一軒の家の庭には、その家の住民と思われる女と子どもたちが、やはり瓦礫の上に投げ出されていた。一番上に幼児が、うつぶせになっているのは、おそらく叩きつけられたのだろう。さるぐつわをかまされた女性が、服をひきさかれて死んでいた。チェックのスカートの女の子が、手を差し伸べるようにして殺され、その隣りに歩いているような姿勢で殺された男の子は、首を針金のようなもので縛られていた。別のガレージには、縛られてトラックにひきずられてきた人々が殺されていた。背の低い小柄な老人が、胸の上に鍵を置いて死んでいた。パレスチナ人たちは、いつか故郷に戻る日のために、かつての自分の家の鍵をいつも持ち歩いている、という話を私は思い起こした。
【『パレスチナ 新版』広河隆一〈ひろかわ・りゅういち〉(岩波新書、2002年)】
・「ベイルート虐殺事件から20年」広河隆一
・パレスチナの歴史:サブラ・シャティーラの虐殺
田文の光彩に満ちた春秋/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
物語は第4巻でクライマックスに至る。敢えてそう書いておこう。宮城谷作品は、ある種の透明感をもって幕を下ろすのが特徴だ。人が歴史に溶け込むような印象を受ける。目の前で躍るように活躍していた登場人物が、再び歴史の彼方へと去ってゆくのだ。
田忌(でんき)と鄒忌(すうき)の政争、白圭(はくけい)の堤防事業、田文(でんぶん)と洛芭(らくは)の運命的な出会い。歴史の歯車が音を立てて回り始める。
「田忌(でんき)将軍のご気性からすると、善を喜び、悪を憎むことがどちらもはげしい。それをけむたがる者は、善の仮面をつけて悪をおこなう」
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
宋江(そうこう)が『水滸伝』の主役となっている意味が初めて腑に落ちた。清らかな権力者は必ず他人にも厳しくなる。当然、恨みを買う場面も増える。気づかぬうちに不満分子が寄り集まる。そこに鄒忌(すうき)が付け込む隙(すき)があったといえる。
斉(せい)の貴族のなかで、いや、中国の貴族のなかで、食客(しょっかく)をかかえはじめたのは、田嬰(でんえい)が最初であろう。
孫ピンの下(もと)で学んだ田文が今度は食客に揉まれながら著しい成長を遂げる。食客は臣下ではない。このため恩を感じても、忠を尽くす義務はない。主人を助ける助けないも彼らの自発による。若き田文は食客たちの心をつかんでゆく。後々彼らは田文を大いに助けることとなる。
――人には他人にいえぬことがある。
それをことばではなく、心でわかることが、ほんとうにわかるということではないのか。真意というものはことばにすると妄(うそ)になる。だから、いわない。黙っていることが真実なのである。
これを私は27歳の時に知った。人生を変えるほどの感動に包まれたことがあった。それを友人たちの前で語ろうとしてやめた。「言葉にすると嘘になるから」と私は言った。もちろん文脈は異なっているが、言葉にできぬ思いという点では一致している。
また、30代半ばではこんなこともあった。後輩の父親が二度にわたって自殺未遂をして行方不明となった。半年後に首を吊った遺体が発見された。風の如く後輩の家を訪ねると、いつもと変わらぬ姿があった。お母さんと妹もニコニコしていた。座卓を囲みしばし沈黙した後、私は後輩の膝を思い切り叩き、「すまん、何もできなかったよ!」と言うなり泣いた。その瞬間、居合わせた全員がわっと声を上げて泣いた。ただ泣いた。泣いて泣いて泣き抜いた。言葉は要らなかった。
長い人生にはそういうことが何度かあるものだ。真の理解は沈黙の底から生まれる。
「文(ぶん)どのはよい声をしておられる。じつにすがすがしい。天と地とが和したような声だ。億万人にひとりの声だ、と申しておこう」
声の響きが大切である。声はその人の生命の反響である。文章は嘘をつけるが、声は誤魔化せない。
――外交は目でするものではない。耳でするものだ。
それが田嬰(でんえい)のかけひきの秘訣(ひけつ)であった。
父・田嬰(でんえい)も声から相手を見抜くことができる人物であった。聞く人が聞けば、おのずと正邪のバイブレーションがわかるものだ。
白圭(はくけい)は私財をなげうって黄河の堤防事業を開始する。商いで稼いだ金を民に返すというのが持論であった。白圭と再会した田文(でんぶん)は右腕として事業の指揮をとる。そこで赤子(あかご)の時、一緒にさらわれた洛芭(らくは)と巡り会う。
田文(でんぶん)は光彩に満ちた春秋を歩む。彼には焦りがない。そして、じっくりと時を待つ肚(はら)ができていた。
数千年の時を超えて英雄が立ち上がってくる。足腰の力がなければ踏みこたえることができない。前屈(かが)みの姿勢で本書を開くべきだ。
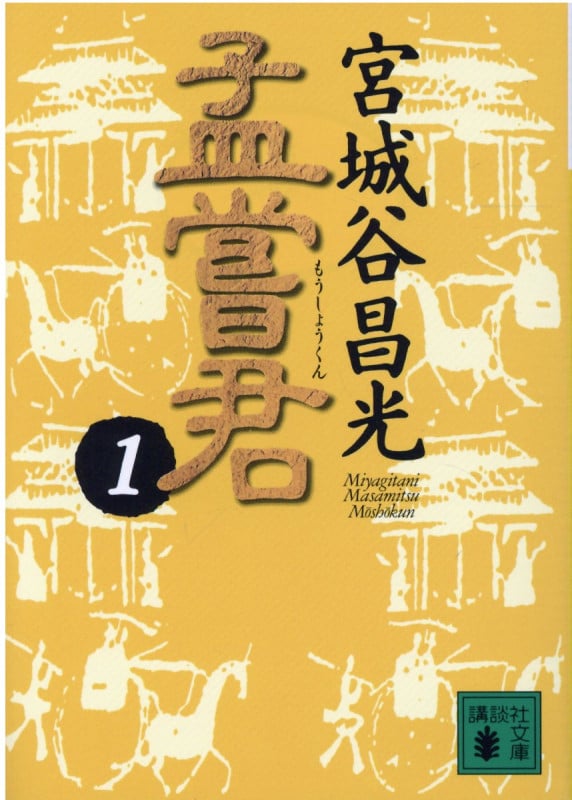




・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
2011-07-15
もの言わぬ死の叫び
2011-07-14
孫子の兵法/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
あしきりの刑を受けた孫ピンは白圭の手で助けられ、九死に一生を得る。
――孫子〈そんし〉に、なにかすごみのようなものが、憑(つ)いたな。
と、白圭は感じていた。からだつきやことばづかいにまるみがあるのは、むかしとかわらないが、ひとつちがったのは目である。目に心の風景がうつるとすれば、孫ピンの目のなかに峻谷(しゅんこく)と峻峰(しゅんぽう)がみえた。さらにいえば、その谷と峰とに霧がかかっている。したがって谷の深さと峰の高さをみきわめようがない。そんな感じであった。
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
艱難(かんなん)が人を玉と磨き上げる。修羅場が胆力(たんりょく)を養う。威厳とはまとうものではない。死を目前にした孫ピンは、生への執着から離れることができたのであろう。
「よかろう。雨や風の日のほかは、庭で教えよう」
と、孫ピンは入門をゆるし、陽のしたでこの熱心な弟子に教学をさずけることにした。
慶■〈けいウン/さんずい+云〉は身ぶるいした。
あたりの空気をうごかしてくる孫ピンのことばは、かつて耳にした孫ピンのことばとはちがい、神韻(しんいん)といってよい深みをそなえている。あえていえば、孫ピンがくぐりぬけてきた苦難の闇の底知れなさと生死の境にあったうつろいやすい微光、そんなものの存在が、足のない孫ピンの容光から慶ウンにつたわってきた。
戦いにむかう兵は、孫ピンが体験したとおなじ闇と微光の世界に投げこまれる。
それらの兵を凱帰(がいき)させるために、どうしても戦略というものがいる。兵とは民である。民の力で国は富むものであり、その民を兵として酷使し、しかも戦陣で死なすことは、国にとって二倍の損害になる。国の威信をたもつ戦いをまっとうして兵を生還させるのが為政者(いせいしゃ)のつとめであろう。だが、どの国もそこまで考えて兵をつかってはいない。
戦略とは、人のいのちの大切さの上に成り立つものである。
末尾の一文を宮城谷の勝手な想像だと嘲(あざけ)るのは簡単だ。しかしながら合理性を極限まで追求すれば必ず一兵卒(いっぺいそつ)に至る。戦争とは所詮命の奪い合いだ。であるならば、孫ピンが生命を重んじたことは自明といえよう。
孫ピンは教えを請われた。ここに教育の原風景がある。日本の近代を開いたのも、剣豪の修行の如く学び抜いた若者たちであった。限定された教育現場から学問の気風は生まれない。野放しの自由から求道の心は芽生えるのだろう。
威王〈いおう〉の目から田忌〈でんき〉をみると、たしかにこの将軍は勇気にすぐれ、つねに敵軍をみくだして、兵をするどくすすめる指揮ぶりで、自軍に不利が生じても一歩も退かぬたのもしさはあるのだが、それをうらがえせば、
――権(けん)に欠ける。
というみかたができる。権は、臨機応変といいかえてもよい。
城を守りぬくことにおいて、生涯、いちども破れることを知らなかった墨子〈ぼくし〉は、じつは武人ではなく思想家であったのだが、かれは権について、
――所体のなかにおいて、軽重を権(はか)る。これを権という。
と、いっている。所体というのは、あたえられた情況ということであろう。そのなかでものごとの軽さと重さをみきわめることが権であるというのである。また、権は、ものごとの是非(ぜひ)をきめることではなく、利害を正すことである、とも墨子はいっている。
戦争は将軍にとってまさに所体といえるであろう。
権に「かり」の意味があるのは知っていたが、かように深い言葉だったとは露知らず。権力とは「かりの力」というよりも「はかる力」なのだろう。公平な分配のために「はかる」のだ。
ということは平衡感覚を欠いた権力は軽重(けいちょう)を誤る。利権に動かされてしまえば、意図的な加減を加える。労働対価は資本家と国家に吸い取られた挙げ句、経済は停滞してゆく。世界で初めてサラリーマンの源泉徴収を導入したのは日本であった。
主人公・田文〈でんぶん〉と実父である田嬰〈でんえい〉を巡るドラマが伏線となっている。
「いや、白圭〈はくけい〉の子ではないのです。白圭もわたしも、あの子をあずかっているにすぎません」
「ほう、して、その父母は──」
田嬰〈でんえい〉の声に、はっと青欄〈せいらん〉は孫ピンをみつめた。
「天、と申しておきましょう」
孫ピンが微笑すると同時に貌弁〈ぼうべん〉が声をたてて笑った。その笑声に天空の雲が破られたのか、月光が台上にさらさらながれ落ちてきた。
孫ピンの智謀が光る。そして田文こと孟嘗君〈もうしょうくん〉は天を動かす逸材に育ってゆく。
遂に田文〈でんぶん〉は田嬰〈でんえい〉の前に進み出た。子は「なぜ私を殺せと命じたのですか」と質(ただ)した。
「五月の子は、身長が門の高さにひとしくなり、父母にとって害になるということだ」(中略)
田文〈でんぶん〉は笑いたくなった。その笑いをこらえたためか、かれの舌鋒(ぜっぽう)はするどく父にむかった。
「人の命運というものは、天からさずかるものでしょうか。それとも、門からさずかるものでしょうか」
田嬰〈でんえい〉はむすっと口をむすんだ。不快そのものの表情である。
田文は父の気色(きしょく)の変化を恐れなかった。さらに、
「人の命運が天からさずかるものであれば、父上はご心配なさることはありますまい。もしも門からさずかるものであれば、門を高くすればよろしいではありませんか。そうすれば、だれがその門にとどきましょうか」
と、からさをこめていった。
田文は既に孫ピンの下(もと)で学んでいた。戦略とは知略であり機略でもあった。機をとらえて変化の波を起こすのが兵法といえる。
戦争というものは、勝つべくして勝つものであり、軍旅をすすめながら勝算を計(はか)るものではない。それは孫子〈そんし〉の兵法の根幹にある考えかたである。
「謀(はかりごと)を帷幄(いあく)の中(うち)に運(めぐ)らし、勝つことを千里の外(ほか)に決する」(劉邦が軍師の張良を称賛した言葉)のが兵法の道である。逆から考えると勝敗の帰趨(きすう)が不明な戦いは避けるべきである。
かのナポレオンも孫子を愛読した。イギリスの軍事史家リデル・ハートはクラウゼヴィッツの『戦争論』を批判し、『孫子』を称揚した。
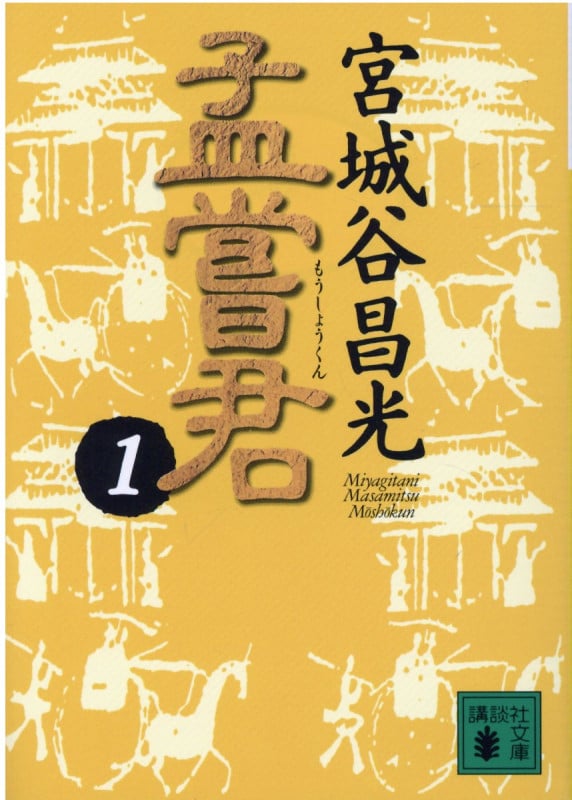




・『孫子』の意義
・兵とは詭道なり/『新訂 孫子』金谷治訳注
・日本のデタラメな論功行賞/『孫子 勝つために何をすべきか』谷沢永一、渡部昇一
・はかるという漢字の多さ/『なんでも測定団が行く はかれるものはなんでもはかろう』武蔵工業大学編
・狂者と獧者/『小村寿太郎とその時代』岡崎久彦
・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
一人一票に関心が湧かない
自分でも信じられないほど一人一票に関心が湧かない。酔っ払った頭で考えてみよう。
都道府県内において一人一票は担保されている。一人一票が崩れるのは他県と比較した場合である。他県と比較する視点は、都道府県を超える範囲に権力を及ぼすことのできる人物だけではあるまいか。つまり国会議員。
判例に基づく一票基準には誤差が含まれている。選挙を比例区のみにしたところで誤差はなくならない。ゼロと1の間には無限が存在するのだ。
一人一票が実現すれば政治はよくなるのだろうか? なるかもしれないし、ならないかもしれない。
一票の格差を金利とすれば、高金利の都道府県に移住する人々がいてもいいはずだ。
頭が回らないので結論を書いてしまおう。一人一票に固執すると、多数決原理主義になるのではあるまいか。
・一票の格差が諸悪の根源なのか?
2011-07-12
自閉症者の苦悩
私がどれほど懸命に努力しても、ほんもののひとたちは、まだ変われと言う、自分たちのようになりなさいと言う。
それがどれほどむずかしいことか彼らにはわからない。気にもしない。私に変わってほしいと思う。私の頭のなかにいろいろなものを入れて、私の脳を変えようとする。そんなことはしていないと彼らは言うが、彼らはそうしているのだ。
【『くらやみの速さはどれくらい』エリザベス・ムーン:小尾芙佐〈おび・ふさ〉訳(早川書房、2004年)】
・自閉症者の可能性/『動物感覚 アニマル・マインドを読み解く』テンプル・グランディン
柳川喜郎
1冊読了。
47冊目『襲われて 産廃の闇、自治の光』柳川喜郎〈やながわ・よしろう〉(岩波書店、2009年)/著者は岐阜県御嵩(みたけ)町の町長を務めた人物で元NHK記者。タイトルからしてクライマックスで襲われるのかと思いきや冒頭に襲撃シーンが。産廃を見直す発言をした柳川に二人の暴漢が襲い掛かり滅多打ちにする。頭蓋骨陥没、右上腕は直角に骨折していた。瀕死の重傷。プロの手口だった。ここから柳川の本当の戦いが始まる。相手は産廃業者の寿和(としわ)工業(韓鳳道〈清水正靖〉会長、当時)と産廃設置を推進しようとする岐阜県&梶原拓知事(当時)、それに暴力団だ。小さな町だからこそ、この国の政治情況が縮図となっている。電話を盗聴され、地元ミニ新聞から攻撃され、岐阜県から圧力を掛けられても、柳川は屈しなかった。本書の中心テーマは住民投票と住民自治である。柳川は自らが犠牲となって民主主義に魂を吹き込んだ。梶原拓知事の意向があったのか、警察は襲撃事件すらまともな捜査を行わなかったことが後に判明する。都道府県が官僚となって市町村の足を引っ張っていることがよく理解できる。産廃を取り巻く闇の深さに圧倒される。
宗教団体法の原型となった「宗教法案」
宗教団体法の原型となった「宗教法案」が最初に登場したのは、明治22年(1889年)のことだった。第14回帝国議会に提出されたもので、時の総理・山県有朋は次のように法案の提出理由を述べている。
「国家ハ信仰ノ内部二立入テ干渉セザルコトハ勿論ノコトデアリマス。併シナガラ其ノ外部二現ハルル所ノ行為ニツキマシテハ……国家ハ之ヲ監督シテ社会ノ秩序安寧ヲ妨ゲズ、又臣民ノ義務二背カザラシメントスルコトハ、是レ国家ノ義務デアルノミナラズ、又其ノ職責二属スルモノト存ジマス」
と述べ、続いて提出理由は宗教団体への恩典の数々を並びたてた内容だった。「兵役の特典」「租税の免除」等々。要するに、監督管理する代わりに、特典が与えられるアメとムチが中身だった。
【『ルポ・宗教 横山真佳報道集 1』横山真佳〈よこやま・みちよし〉(東方出版、2000年)】
2011-07-11
律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅/『孟嘗君』宮城谷昌光
・『管仲』宮城谷昌光
・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光
・大いなる人物の大いなる物語
・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅
・孫子の兵法
・田文の光彩に満ちた春秋
・枢軸時代の息吹き
・『長城のかげ』宮城谷昌光
・『楽毅』宮城谷昌光
・『香乱記』宮城谷昌光
風洪(ふうこう)と公孫鞅(こうそんおう)は行動を共にする。やがて、それぞれが進む道へと分かれてゆく。人生の転機は出会いによってもたらされ、鮮やかなアクセントをつけて調子を変える。
いかなる人物とどのように出会うか――そこに人生の縮図が表れる。
人を家にたとえると、目は窓にあたる。窓は外光や外気を室内にとりいれるが、室内の明暗をもうつす。そのように目は心の清濁や明暗をうつす。
寿洋(じゅよう)の目が少年のようだ、と風洪(ふうこう)が感じたのは、寿洋という商人が少年の純粋さをもちつづけてきたということであろうが、寿洋の心が商略という腥風(せいふう)の吹きすさぶ道を歩いてきたにもかかわらず、汚れなかったということであり、さらにいえば、かれを襲った不幸をはねかえし、かれを浸(ひた)した幸福におぼれなかったということでもあり、そのことはとりもなおさず、常人ばなれのした信念があるということである。
風洪はそう考えた。
【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】
人に噂はつきものである。しかし噂には責任が伴わない。又聞きも多く、熟慮や吟味を欠く。相手を見つめるのは「自分という鏡」だ。要らぬ先入観や勝手な思惑があれば、映像は歪んでしまう。
寿洋という商人がひとすじなわでないことくらい、風洪にもよくわかる。
──が、あの老人は、善人だ。
と、心のなかで断定した。その人をみきわめるには、初対面こそがもっとも重要である、と風洪はおもっている。その点、寿洋という老人は素直に心にはいってきた。
・ひらめき=適応性無意識/『第1感 「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい』マルコム・グラッドウェル
パッと見た瞬間、生命(いのち)から滲み出る何かがある。それは匂いに近いものだ。繕(つくろ)えば、その繕い方から性根が垣間見える。威儀や振る舞いから伝わるものは多い。
公孫鞅(こうそんおう)は風洪(ふうこう)の妹を娶(めと)り、官職に就く。魏(ぎ)の恵王(けいおう)からは蔑ろにされたが、秦(しん)の若き君主・孝公(こうこう)は公孫鞅の熱弁を理解できた。官位を得た公孫鞅は法令改正を思い立つ。
公孫鞅(こうそんおう)は、連日、孤立無援の論陣を張っていた。
かれの思想の根幹にあるのは、
──いかに国を富ませ、兵を強くするか。
ということであり、そのためには国家の意志を統一しなければならないということであった。
たとえば法も国家の意志のあらわれであるが、その法が国民すべてに適用されなければ、効力をうしなってしまう。が、現実には公族や貴族には適用されていない。おなじ罪を犯しても、庶民は罰せられるが、貴門の者はゆるされる。
国民とひとくちにいうが、公民と私民とがあり、公民と私民とでは賦税(ふぜい)の率がちがい、私民のあいだでも、主君がちがえば賦税の重さがちがう。
こまなことをいえば、一升(しょう)の量でも、各領地によってちがうのである。
そのようにばらばらなものがよりあつまって秦(しん)ができている。それではいくら君主が心をくだき骨をけずって善政をおこなおうとしても、だれの目にもみえる業績とはならない。
このさい、ことごとく旧弊(きゅうへい)を廃し、新制度をしきたい。それが公孫鞅の主張であった。
富国強兵は政治の原点であろう。政治は経済と軍事に尽きる。ここを見落とすと政治は虚言(きょげん)と化す。法律や制度を見直し、予算を組むのも富国強兵のためである。
孝公(こうこう)は慎重であった。
改革に賛同する者の声が反対する者の声にかき消えないほどのたしかさをもつまで、自分の意中をいわず、議論をみまもりつづけた。
ふたつの声の量が、ひとしくなった。
臣下の目がそろって孝公を仰いだ。
──もうよかろう。
と、おもった孝公は、おもむろに口をひらいた。
「窮巷(きゅうこう)は怪(かい)多く、曲学(きょくがく)は弁(べん)多しときく。愚者(ぐしゃ)の笑いを智者は哀しみ、狂夫の楽しみを賢者は憂える。世にかかわりて、もって議するも、わしはこれを疑わず」
孝公がそういった瞬間、秦(しん)は改革の第一歩をふみだしたことになる。
窮巷、すなわちかたいなかに住んでいると、世知に欠け、なんでも怪しむようになり、曲学、つまり正しい学問をしていない者はいたずらにしゃべるだけである。愚かな者が笑ったことを知恵のある者は哀しみ、狂人の楽しむことを賢人は憂えるものである。世俗の旧習にとらわれた議論がどんなにおこなわれようとも、わしには信念がある。
孝公はそういったことになる。
その信念とは、秦を改革することであり、それは国法を変ずることになるので、当時のことばとして、
「変法」
である。議場は粛然(しゅくぜん)とした。
変法が行われたのは紀元前359年のことである(Wikipedia)。公孫鞅(こうそんおう)は法令に信賞必罰の魂を吹き込んだ。
中央の目がとどかないことをさいわいに、かってに法令を変える悪辣(あくらつ)な官吏もいる。法令の一字を加えても消しても死刑にする。公孫鞅(こうそんおう)がそういったとき、
「一字で、死刑か」
と、孝公はつぶやき、目をみはった。
「さようです」
公孫鞅は平然といい、ことばを継(つ)いだ。
不公平があれば民は法に従わない。役人の匙(さじ)加減で運用が変われば贈収賄の温床となる。公孫鞅(こうそんおう)は厳罰をもって施行に臨んだ。
とにかく公孫鞅の提言は重大なことをふくんでいた。公族や貴族の領地では法令の書きかえなど日常茶飯事(さはんじ)であったのに、それができなくなった。各地方の役人は法令の内容を人民にろくにしらせずに、独断でとりしまりをおこなっていたのに、こんどは法令の全文を人民に告げ、なおかつ説明しなければならない。それをおこたり人民が罪を犯すと自分が罰せられるのである。いわば人民もその法令によって、官吏(かんり)を監視できるのである。違法の官吏がいれば、法官の長に質問し、その質問は公表されるからである。
法令が人民から見えるようにしたことで、役人のインチキを未然に防いだ。この他にもありとあらゆる知恵を巡らした。
「法令は民の命です。政治をおこなう本(もと)です。それなくして民を守ることはできません」
と、あえて強く言上した。
今の官僚にこの気概がありやなしや。国家を治めるどころか、我欲を治めることもできずに自らの天下りを確保する姿は浅ましい限りである。政治は義を失って利で動くようになってしまった。既に政治とは「商い」をする言葉へと堕落した。
孝公(こうこう)の太子が法を犯した。
「太子をさばくのですか」
と、法官はうろたえぎみにいった。
「そうです。法の下には身分の上下はありません。わが君が罪を犯せば、たとえ一国の君主でも、刑罰をうけねばなりません。太子でも容赦はなりません」
公孫鞅(こうそんおう)は厳然としていった。
太子駟(たいしし)の罪状はあきらかとなり、有罪と決した。が、一国の嫡子に刑をおよぼすことをはばかり、傅(ふ)の公子虔(けん)を■(ぎ/鼻+リ)、師の公孫■(こうそんか)を黥(げい/いれずみをする)刑に処した。翌日から法令を非難する民の声はぴたりと熄(や)んだ。
公正さは厳しさを伴う。身内への甘さが腐敗を生む原因となる。諸葛孔明は泣いて馬謖(ばしょく)を斬った。
東日本大震災で原子力行政と東京電力の欺瞞(ぎまん)が明るみに出た。福島県の自殺者は昨年(4-6月期)に比べて2割も増えている。菅首相は「白紙に戻す」としておきながら、原子力推進を継続する旨を言明している。
誰一人罰することなく、誰一人責任をとっていない。官僚は今頃、新しい安全神話の作成に着手しているような気がする。
史実によれば公孫鞅(こうそんおう)は、この太子によって車裂の刑に処せられている。逃亡を試みたが、自分で作った法令が仇(あだ)となった。
公孫鞅(こうそんおう)が心血を注いで作り上げた法令は、唐の時代にまで影響を及ぼし、更には日本へと伝わった。
一方、風洪(ふうこう)は白圭(はくけい)と改名し、商人の道を歩み始める。
「利の世界で生きようとなさる」
「いえ、仁義の世界で生きるつもりです」
「ほう」
尸子(しし)は微笑をふくんだ。
「義を買い、仁(じん)を売ります。利は人に与えるものだとおもっております」
社会的責任において買ったものを心で売る。そこで得た利益を世の人に還元するということである。
「かつてそんな商人はいなかった。もしあなたがそれをなせば、あなたは万民に慕われるだろう」
と、尸子は楽しげにいった。
この物語は読み手の背中を垂直にする。人の歩むべき道が確かに存在することを教えてくれる。
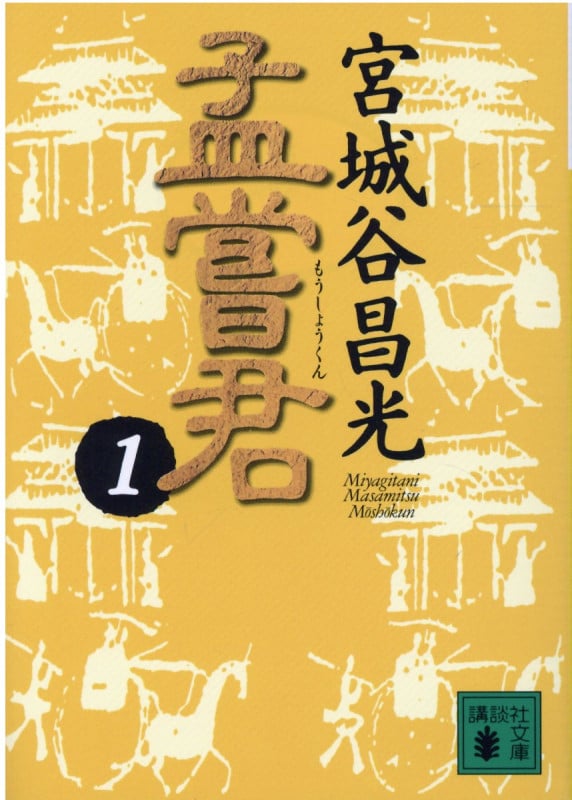




・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次
夢に関する覚え書き
夢1 睡眠時の夢について考える連続ツイート。夢のメカニズムについてはまだわかっていない。浅い眠りに陥るレム睡眠中に見るとされ、ノンレム睡眠時は発現されないと考えられていた。 しかし、最近ではノンレム睡眠時にも夢を見ることが確認されている。http://bit.ly/dphJ8r
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
・Wikipedia
夢2 夢の語源は「寝目(いめ)」で、「寝」は「睡眠」、「目」は「見えるもの」の意味である。平安時代頃より「ゆめ」に転じ、「はかなさ」など種々の意味で比喩的にも用いられるようになった。夢が「将来の希望」といった意味で使われ始めたのは近代以降。http://bit.ly/ajxNsX
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
・語源由来辞典
夢3 部首は下の「夕」で、「夕方」「夕べ」の「夕」ですから、「暗い」とか「よく見えない」という意味ですから、なんとなくわかります。それで上半分ですが、これは「かん」という漢字(昔の字なのででないのです... http://bit.ly/cQPYmW
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
・続き
・夢という漢字の由来について
夢4 荘子「胡蝶の夢」 http://bit.ly/dBSNa6
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
・荘子「胡蝶の夢」
夢5 『枕中記』(ちんちゅうき)「邯鄲の夢」(かんたんのゆめ) http://bit.ly/ahFiiP
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
・『枕中記』(ちんちゅうき)「邯鄲の夢」(かんたんのゆめ)
夢6 脳は睡眠中も起きている時と同等の活動をしていることが明らかになっている。睡眠時は五官からの情報が遮断されている。そして意識がない。物理的な現象が夢に影響を与えることはあるが、これは半覚醒状態といえよう。夢は無意識領域に現れた意識と考えることが可能だ。
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
夢7 私は夢を幽霊のようなものだと考えている。前の日に感じた違和感、無念、恨みつらみといったものが化けて出てくるのだ。その思いや思念を何らかの形で社会の枠組みに合うように変換しているのだと思う。脳内ネットワークが社会ネットワークと摺り合わせをするのが夢なのだ。
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
夢8 この考えが正しければ、幽霊が死んでも死にきれない怨念を表しているように、夢は眠っても眠りきれない中途半端な状態といえる。虐殺や事故死が痛ましいのは、そこに我々が「無念の物語」を描くためだ。だが、平均寿命まで生きたとしても「中断された」ような死に方をする人は多い。
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
夢9 夢は現実と対比される。夢か現(うつつ)か幻か。その一方でぼんやりと人生を過ごすことを酔生夢死という。これは私にいわせれば「夢生現死」となる。完全に意識が休んで(=死んで)いれば夢は見ない。だから夢を多く見る人ほど、社会で違和感を覚えたり、恐れを抱いているように思う。
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
夢10 物事に熱中することを無我夢中という。これまた本当は「無我眠中」である。なぜなら夢には「我」(が=意識)が存在するからだ。完全に生きるとは「生に没頭する」ことだ。生を味わい尽くすことだ。ここにブッダが説いた無我の境地がある。大切なのは違和感を言葉にすることだ。
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
夢11 違和感を放置しない。自分の感覚が狂っているのか、周囲が誤っているのかを厳しく問うべきだ。「おかしい」と思ったら声を上げることが正しい。違和感をうやむやにしている人は判断力が劣化してゆく。生きるとは疑問を乗り越えてゆくことでもある。生の炎を燃焼させよ。夢を見るな。以上
— 小野不一 (@fuitsuono) September 22, 2010
現象に関する覚え書き
・川はどこにあるのか?
・月並会第1回 「時間」その一
・月並会第1回 「時間」その二
・時間とは記憶の残像である
・現象に関する覚え書き
・『ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想入門 豊かな人生の技法』ウィリアム・ハート
川を見る。次から次へと流れ去る水を見つめる。川はどこにあるのだろう? 川を自宅に持ち帰ることはできない。とすると川に実体はないのだろう。水が干上がれば、それは川ではない。つまり川が流れているのではなく、流れそのものが川なのだ。私の目の前にあるのは「川という現象」だ。
— 小野不一 (@fuitsuono) August 30, 2010
打ち上げ花火を見る。一筋の光が天を目指し、爆発する。地面を揺るがす音と共に七色の炎が放射状に広がる。光の雫は重力に抗えず、垂れかかった涙のように闇の中へ消えてゆく。夜空に花火の残像が浮かぶ。花火もまた現象である。 RT @fuitsuono: 川を見る…
— 小野不一 (@fuitsuono) August 31, 2010
花を見る。やがて花は枯れる。遂に跡形もなくなる。花という現象。人を見る。人の一生を見る。やがて人は死ぬ。骨も消え去る。人という現象。私も川も現象である。実体はない。あるのは流動性だけ。変化こそ本質である。これを諸行無常という。
— 小野不一 (@fuitsuono) August 31, 2010
生命現象とは「時間的存在」なのだろう。 RT @krishnamurtibot: このように、時間の永続性があり、また最後には到達される真理という観念に対して思考が付与した永遠性がある。
— 小野不一 (@fuitsuono) August 14, 2010
私が在(あ)るのではなく、私という現象が在る。


