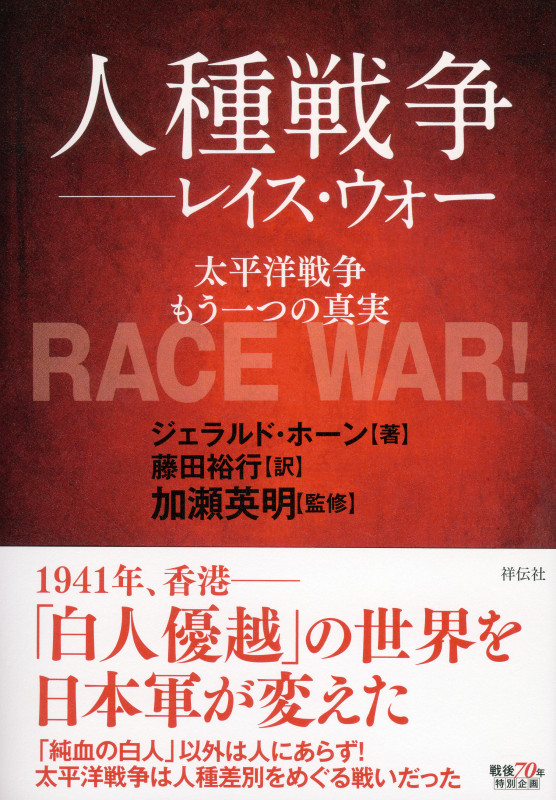・『たった一人の30年戦争』小野田寛郎
・『F機関 アジア解放を夢みた特務機関長の手記』藤原岩市
・戦前の高度なインテリジェンス
・『チベット潜行十年 』木村肥佐生
・『チベット旅行記』河口慧海
・『城下の人 新編・石光真清の手記 西南戦争・日清戦争』石光真人編
・『サハラに死す 上温湯隆の一生』長尾三郎編
「あなたは親切心で言ってくれるのでしょうが、私は、ヒマラヤを、この体でこの二本の足で七度も越えて鍛え上げているのだ。私がこんな姿をしているのは、あなたのそんな親切なめぐみを、待ち望んでしているのとは、まったく意味が違う。私達は戦争には負けた。しかし、私は、精神的には負けてはいないのだ」
日本人と同じ顔をした、栄養状態のよいこの米人は、顔色ひとつ変えずに私のはげしい言葉を聞くと、その軍服を片づけた。
私とこの通訳とは、さらにその後半年、この個室で同じ毎日をつづけた。私が、自分の足跡の一切を、相手の質問の尽きるまで語りつくしたときは、完全に一年間が経過していた。通訳がこの間に、私から調べ上げた調書の原稿は数千枚にも及ぶうず高いものだった。彼は、この功によって二階級特進した。
八年間死地をくぐり、日本政府から一顧にも付せられなかった私は、この間、日当一千円を米軍から受取っていた。当時、私にはかなり高額の金である。私は貴重な情報を、アメリカに売るのかという、心のとがめを感じないわけではなかった。が、それならば何故、外務省が私んしかるべき態度をとらなかったのかという反撥の心があった。すべて、敗戦のしからしめるところであったと思う。しかし私は、通訳と向き合う生活をはじめて間もなく、すすめてくれる旧師もあって私なりのひそなか決心を固めていた。なんのためという具体的な目標があったわけではないが、決してGHQには売らない八年間の自分の足跡というものを、自分のものとして真実の記録として残すことを思い立ったのである。
【『秘境 西域八年の潜行』西川一三〈にしかわ・かずみ〉(芙蓉書房、1967年/中公文庫、1990年)】
西川一三は戦前の情報部員である。チベットに巡礼に行くモンゴル僧「ロブサン・サンボー」(チベット語で「美しい心」)を名乗り、チベット・ブータン・ネパール・インドなど西域秘境の地図を作成し地誌を調べ上げた。その活動はなんと敗戦後の1949年まで続いた(敗戦は1945年)。帰国後、直ちに外務省に報告をするべく訪ねたが、全く相手にされなかったという。直後にGHQから出頭せよとの命令があり、西川の情報を引き出すべく1年にも及ぶ取り調べが行われた。
小野田寛郎〈おのだ・ひろお〉のように敗戦後も戦い続けた日本軍兵士や諜報員は数多くいた。たぶん数千人規模でひょっとすると万を超えていた。大半の兵士はアジア諸国独立のために加勢した。そのまま現地で生活をし続け、骨となった人々もまた少なくない。大東亜会議で掲げた理想の旗は日本が敗れても尚、アジアの地で高々と翻(ひるがえ)った。そんな彼らに国家は報いることがなかった。否、見捨てたといってもよい。こうしたところに真の敗因があったと思われてならない。
日本人は個々人の志操は高いのだが組織になると「村」レベルの惨状を露呈する。武士はいたものの貴族が存在しなかったゆえであろうか。社会学の大きなテーマになると個人的には考えているのだが、小室直樹が触れている程度で手つかずのような気がする。厳しい階級制度がなかったことも遠因の一つだろうし、天皇陛下の存在が悪い意味での安心感を生んでいることも見逃せない点である。長らく外敵の不在が続いたことも体制がシステマティックにならなかった要因だ。そして体制が変わると閥(ばつ)がはびこるのも我が国の悪癖であろう(戦後、組織化に成功した日本共産党や創価学会においても同様である)。優秀な人材がいながらも江戸時代に総合的な学問が発展しなかったのも同じ理由と思われる。
時代は変わっても日本人には職人肌なところがあるように思う。オタクなどが好例だ。現代にあっても国際的な舞台で活躍する個人は多い(中村哲〈なかむら・てつ〉やビルマの内戦を止めた井本勝幸など)。スポーツ、芸術、音楽、美術においても白人と伍し、漫画に至っては世界を牽引(けんいん)している。我々のDNAは個人や小集団で発揮するようにできているのかもしれない。
官僚が支配する息苦しい日本で出世競争に血道を上げるよりは、若者であれば単独者として世界を目指せと言いたい。